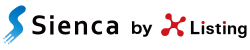ランディングページ(LP)とは?種類や作り方、成果を上げるポイントを解説
インターネット上で商品やサービスを売りたい、問い合わせを増やしたい、イベントの参加者を集めたい――そんなときに効果を発揮するのがランディングページ(LP)です。LPは訪問者に特定の行動を取ってもらうために設計された1ページ構成のWebサイトで、効果的に活用すれば高いコンバージョン率を実現できます。
しかし、ただ作るだけでは成果につながりません。デザインや構成、コピーライティング、ユーザーの動線設計など、さまざまな要素を最適化する必要があります。本記事では、ランディングページの基本概念から制作手順、成果を最大化するための改善ポイントまでを網羅的に解説します。
初心者の方でも理解しやすいように、具体例やチェックリストを交えながら詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。LPOやABテストの実施や施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら
LPO入門ガイド。LPOの基本的な考え方と重要性を解説。ランディングページのコンバージョン率を向上させたい方必見。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
ランディングページ(LP)とは?

ランディングページ(LP)とは、特定の成果を得ることを目的に作られた1枚もののWebページです。一般的に訪問ユーザーに資料請求・問い合わせ、メルマガ登録、商品の購入など具体的なアクション(コンバージョン)を起こしてもらうことが目的になります。ページ内の情報や導線はこのゴール達成に向けて最適化されており、訪れたユーザーを一つの行動へ誘導するよう設計されています。
ホームページ(HP)との違い
ホームページ(HP)は、企業やブランド全体の情報を網羅的に掲載し、訪問者に幅広く情報提供するのが主な役割です。
一方でランディングページは、扱うテーマや商材を絞り込み、ユーザーに「このページで提案する行動」を取らせることだけに集中しています。そのためホームページが複数の下層ページを持つサイト構成であるのに対し、ランディングページは基本的に縦長1ページ完結の構成です。また、ランディングページは多くの場合Web広告やSNSからの誘導先として使われ、SEO(検索流入)を前提としないケースもあります。逆にホームページは検索エンジンやSNS経由でのアクセスを想定し、継続的に情報更新してサイト全体の集客力を高める役割があります。
商品ページとの違い
ランディングページは基本的にナビゲーションメニューを持たず単一目的に特化している点で異なります。ホームページ内の通常の「商品・サービス紹介ページ」では関連商品へのリンクや他の情報も掲載されますが、ランディングページではユーザーの注意を分散させる要素を極力排除し、一つの商品やオファーに集中させます。そのため、例えば自社の商品ラインナップごとにそれぞれ専用のランディングページを用意するといった運用も必要になります。
ランディングページの種類
ランディングページの種類には、目的やターゲットに合わせて多彩なパターンが存在します。商品やサービスの魅力を効果的に伝え、コンバージョン(具体的な行動)へと導くために作られるページであり、ビジネスのマーケティング戦略上、非常に重要な役割を果たしています。企業のブランド認知度向上や売上増加、見込み客との関係構築など、多岐にわたるメリットが得られます。
新規リード(見込み客)獲得用ランディングページ
新規リード(見込み客)獲得用のランディングページでは、資料請求や無料トライアルへの登録フォームをゴールとします。見込み客の獲得を重視した構成で、冒頭ではサービス概要やメリットを簡潔に提示し、ホワイトペーパーなどのダウンロード特典を設定することで、潜在顧客のメールアドレス収集や問い合わせの増加を目指します。
単品商品の直接販売用ランディングページ
単品商品の直接販売を目的としたランディングページは、セールスに特化した構成が特徴です。その場で購入が完結できるように設計し、商品の特徴やメリット、価格やキャンペーン情報などを強調して購入欲求を高めます。また、限定割引や特典を提示することで、さらに購買意欲を刺激する仕掛けを取り入れる場合もあります。
キャンペーン特化型ランディングページ
キャンペーン特化型ランディングページは、期間限定セールやイベント申込みなど特定のキャンペーン告知に集中して訴求を行います。限定性や希少性を強調して購買や申し込み意欲を高めるのがポイントで、カウントダウンタイマーや残り在庫数の表示といった緊急感を演出するコンテンツを取り入れることで、短期的に高いコンバージョンを狙います。
採用募集用ランディングページ
採用募集用のランディングページは、求人応募の獲得を目的として設計されます。企業の魅力や募集要項をわかりやすく伝えるだけでなく、実際の職場環境や社員の声なども盛り込むことで、応募者に安心感を与えます。応募フォームや問い合わせ先を明確に設置することで、スムーズな応募を促し、企業との接点をつくりやすくする工夫が大切です。
セミナー・ウェビナー告知ランディングページ
セミナーやウェビナーの告知を目的としたランディングページは、参加者を集客するための情報発信に重点を置きます。開催の目的や得られるメリット、講師のプロフィールなどを魅力的にまとめ、参加意欲を高める工夫を凝らします。開催日時や場所(オンラインの場合は使用するツールなど)をわかりやすく提示し、申し込みフォームへの導線を確保することが重要です。
このように、ランディングページは目的やターゲットに応じて構成や訴求ポイントが変化します。ターゲットが抱える課題を明確にし、それに応える提案やストーリーを盛り込むことが成功の鍵となり、戦略的に設計・運用することで、大きなマーケティング効果を生み出すことができるでしょう。
株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。LPOやABテストの実施や施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら
LPO入門ガイド。LPOの基本的な考え方と重要性を解説。ランディングページのコンバージョン率を向上させたい方必見。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
ランディングページ制作フロー
ランディングページの制作は企画設計から公開後の改善までの一連の流れを踏みます。以下に代表的な制作フローを示します。
目的・ターゲットの設定(企画)
まずランディングページの最終ゴール(KGI)と数値目標(KPI)を定めます。商品の購入数○件、問い合わせ件数○件など具体的な目標値を設定し、プロジェクトメンバーで共有します。同時にペルソナ(具体的な想定顧客像)の設定も重要です。ターゲットとなるユーザーのニーズ・課題をリサーチし、「誰に何を伝えるランディングページか」を明確にします。
構成案・ワイヤーフレームの作成
次にランディングページの全体構成を検討します。伝えるメッセージの順序や各セクションの内容を決め、ワイヤーフレーム(設計図)に落とし込みます。ワイヤーフレームでは見出し、テキスト、画像配置、CTAボタン位置などページの骨組みを設計します。後のデザインやコーディングはこの設計図に沿って進めるため、LP制作工程の中でも重要なフェーズです。
デザイン・コンテンツ制作
ワイヤーフレームが固まったら、実際のコンテンツ制作に入ります。
まずコピーライティング(テキスト原稿作成)を行います。ランディングページの顔となるファーストビューのキャッチコピーは特に重要で、訪問者がページを読み進める気になるかを左右します。併せてボディ部分の見出し・本文、箇条書きリストやCTA文言などもターゲットに響く表現を考えます。コピーと並行してビジュアルデザインも進めます。
ワイヤーに沿って画像素材や配色、フォントなど視覚的要素を作り込みます。必要に応じて一時的にダミーテキストを配置しつつ、テキスト確定後に差し替える形で進めることもあります。
開発・実装(コーディング)
デザインカンプ(完成デザイン)ができたら、Webページとして表示できるようコーディングします。
HTML/CSSやJavaScriptを用いて実装し、レスポンシブ対応(スマホ表示対応)や各ブラウザで崩れなく表示されるか等をチェックします。最近ではノーコードのLP作成ツールを使う場合もありますが、細かなカスタマイズやトラッキング設置にはコーディングが必要になることもあります。
公開・検証・運用改善
実装が完了したらランディングページをサーバーにアップして公開します。しかしランディングページは公開して終わりではなく、公開後の効果検証と改善(LPO:ランディングページ最適化)が重要です。
公開後にアクセス解析でコンバージョン率や離脱率を計測し、仮説に基づいてページの修正やABテストを行います。例えばCTAボタンの色や文言を変更した別バージョンを試し、成果が良い方を採用するといった改善サイクルを回します。このように運用しながらランディングページの精度を高め、目標達成に向けてチューニングしていきます。
ランディングページで成果を出すためのポイント

効果的なランディングページに仕上げるために、ユーザー心理を踏まえた訴求やデザイン上の工夫が欠かせません。以下に主なポイントを挙げます。
CTA配置と設計
CTA(Call To Action)ボタンはコンバージョンへの入口となる重要な要素です。ユーザーの視線を集めるページ上部の目立つ位置に配置し、スクロール後も見逃されないようページ内に複数回設置すると効果的です。
ボタンのデザインはサイトの他部分と色味を変えて強調し、サイズも大きめにしてひと目で「クリックすべき」と認識できるようにします。文言も「資料をダウンロード」「今すぐ無料登録」など具体的で行動を促す表現を用い、必要に応じて「※○名限定」「期間限定」など緊急性・希少性を訴求してユーザーの背中を押します。

説得力のあるコピーライティング
ランディングページのテキストは単に商品説明をするだけでなく、読み手の心を動かし行動につなげるセールスライティングの観点で作成します。
ユーザーの抱える悩みや課題に共感し、それを解決できることを具体的に示すことが重要です。「どのような問題を解決できるのか」「利用すれば将来どう良くなるのか」を明確にイメージさせるコピーを書きましょう。例えばメリットを数字で示したり、「〜できるようになります」と未来の姿を描いたりすると効果的です。
また根拠となるデータや実績を交えて信頼性を高める表現も盛り込み、ユーザーが納得して行動できるだけの情報と言葉を提供します。
視線誘導を意識したデザイン
デザイン面では、ユーザーが読み進めやすく、重要ポイントに視線が集まるレイアウトを心がけます。
文章や画像の配置・色使いによって、人間の視線の流れをコントロールすることができます。例えば適切な強弱(メリハリ)を付けて強調したい情報を目立たせたり、指し示す矢印や余白の使い方でユーザーの目線を次の要素へ自然に誘導したりします。
特にCTAボタン周辺は背景とのコントラストを強くし、周囲から浮き出るようなデザインで「ここを押して」と視線を集める工夫も有効です。ページ全体としては、見出し→本文→CTAという行動までの筋道が一目で理解できるレイアウトを構築し、ユーザーの思考を迷わせないことがポイントです。
ABテストの活用
ランディングページの成果を最大化するには分析と改善のPDCAサイクルが欠かせません。
その中でも効果的なのがABテストです。デザインやコピーの異なる2パターン(AとB)を用意し、それぞれ一定のユーザーにランダムに表示してコンバージョン率などの指標を比較します。テストでは変更する要素を一つに絞り(ボタンの色だけ変えるなど)、統計的に有意な差が出るか確認します。
例えば「CTAの文言Aパターン vs Bパターン」で実施し、良い結果を出した方を正式採用するといった形です。ABテストを継続的に繰り返すことで、ランディングページの各要素をデータに基づき最適化していくことができます。ツールとしてはOptimizelyなどの専用サービスを使うと便利です。


ランディングページの構成テンプレート
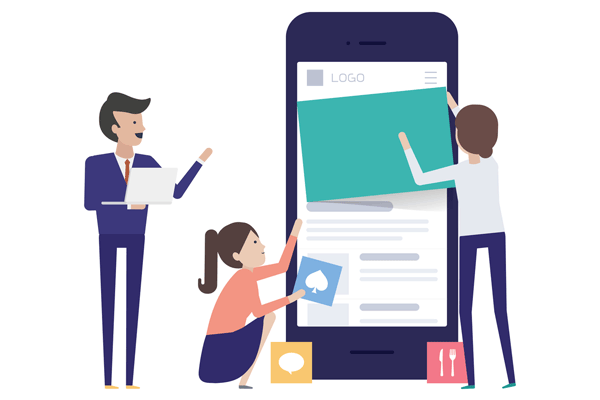
効果的なランディングページには定番ともいえる構成の型があります。業種・商材に応じて細部は変わりますが、多くのランディングページで採用されている基本レイアウトを押さえておきましょう。一般的には以下のような順序で情報を配置します。
ファーストビュー(第一印象部分)
ページ最上部の目に飛び込んでくるエリアです。キャッチコピー、キービジュアル(メイン画像)、そしてCTAボタンで構成されることが多く、「何の商品・サービスなのか」をひと目で伝える役割があります。
ユーザーの興味・関心を引き付け、スクロールして続きを読みたいと思わせることが目的です。例えばキャッチコピーでベネフィット(得られる結果)を端的に示し、魅力的なビジュアルで直感的に訴求します。ファーストビュー次第でユーザーの離脱率が大きく変わるため、最重要パートといえます。
課題提起(ニーズ喚起)
ユーザーの抱える問題点に気付かせ、「自分ごと」としてランディングページの内容を読み進めてもらうためのセクションです。例えば「○○でお困りではありませんか?」と問いかけたり、現状の課題をデータや具体例で示したりします。
ユーザーに課題を認識させ共感を得ることで、解決策への関心を高める狙いがあります。この部分で「そうそう、これが知りたかった」と思わせられれば、次の解決策提示までスムーズに読んでもらえます。
解決策・商品サービス紹介
課題提起に続けて、その課題を解決する具体的な手段こそ本商品の提供価値であることを示します。
ランディングページの主役である商品・サービスの特徴やメリットを詳しく紹介し、ユーザーの悩みをどう解決できるかを説明します。ここでは箇条書きや図表、画像なども使いながら、メリットや他社との差別化ポイントを分かりやすく伝えます。
また必要に応じて活用事例や使用方法、導入プロセスなどを盛り込み、ユーザーが利用後の具体的なイメージを持てるようにします。論理的な説明だけでなく感情にも訴えることで、「これなら自分の問題が解決できそうだ」と感じてもらうことが重要です。
信頼性の訴求
ユーザーが不安を感じず行動できるよう、信頼性を補強する要素も欠かせません。
具体的には導入事例・お客様の声(満足した顧客の testimonial)や、第三者評価(〇〇賞受賞、〇〇認定企業など)を掲載します。実際の利用者の声を載せることで共感や安心感を与え、数字(実績件数や効果データ)を示すことで根拠を示します。
また価格表やFAQ(よくある質問)を設けて疑問点を解消し、安心して次のアクションに進める状態を作ります。信頼性の訴求によってユーザーの心理的ハードルを下げ、ランディングページの説得力を高めます。
クロージング(最終CTA)
ランディングページの最後には改めて行動を促すクロージングセクションを設けます。
内容としてはページ全体の要点を簡潔に振り返りつつ、CTAボタン(コンバージョンボタン)を再度配置する形です。最後まで読んだユーザーに対し、「では具体的に申し込んでみよう」と背中を押すパートになります。ランディングページの締めくくりとして強力なオファー(期間限定特典や無料トライアルなど)を提示し、今すぐ行動しないと損だと思わせる工夫もよく行われます。
クロージングのCTAボタンは大きく目立つデザインにし、クリック後のランディング先(フォームや購入ページ)にスムーズに繋げます。
以上がランディングページの基本的な構成要素です。【ファーストビュー→課題提起→解決策提示→信頼性補強→クロージング】という流れで、ユーザーの心理を段階的に高めながらゴールへ導く構成になっています。これらは業種を問わず汎用的に使える「王道パターン」ですが、業種ごとの成功パターンも存在します。扱う商材やターゲットによって最適な訴求方法は異なるためです。
例えばBtoC商品の販売では、ランディングページ上で直接購入まで完結させるために他の業種以上に「売ること」に特化した作りになっているのが特徴です。キャッチコピーやビジュアルで商品の魅力を徹底的にアピールし、スペックやベネフィットを画像や動画も駆使して直感的に伝えます。またCTAボタンも大きく目立つデザインにして購入意欲を刺激します。
一方でBtoBサービスでは、ユーザーが初回訪問ですぐ契約まで至ることは少ないため、問い合わせや資料請求など複数のCTAを用意して見込み客を逃さない工夫をするのがおすすめです。
たとえば「資料ダウンロード」「無料トライアル」「見積依頼」など段階的なCTAを設置し、ユーザーの検討度合いに応じて選択できるようにします。またBtoBでは意思決定に時間がかかる分、グラフや比較表で効果を分かりやすく伝えたり、料金プランを丁寧に説明して不安を取り除くコンテンツが重要になります。
このようにランディングページの基本構成は共通しつつも、業種・サービス特性に応じて強調ポイントや情報量を調整することが成功のカギです。自社の商材に合った構成パターンを検討し、ユーザーが必要とする情報を過不足なく盛り込むようにしましょう。
株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。LPOやABテストの実施や施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら
LPO入門ガイド。LPOの基本的な考え方と重要性を解説。ランディングページのコンバージョン率を向上させたい方必見。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
ランディングページの作成や改善、分析に役立つおすすめツール
ランディングページを作るうえでは、専門ツールやプラグインの活用も有用です。ここではLP制作に役立つツール、分析に使えるツール、SEO対策に役立つツールを紹介します。
ランディングページ作成ツール
ノーコードまたはローコードでランディングページが作れるサービスです。
代表的なものにWix、Unbounce、Instapage、WordPress+Elementor、HubSpotランディングページビルダーなどがあります。これらはドラッグ&ドロップの直感的な編集機能や豊富なテンプレートを備えており、Web制作の知識がないマーケターでも比較的簡単にランディングページを作成可能です。
例えばUnbounceはA/Bテストや解析機能も内蔵されており、LPOまで一貫して行えます。
国産のサービスではペライチが人気です。ペライチは国内企業にも多く利用されており、数ステップの操作で公開まで完結する手軽さが特徴です。数多くのテンプレートが用意されており、画像とテキストを入れ替えるだけで体裁を整えられるため、LP制作を内製化したい場合に有力な選択肢となります。
アクセス解析・ユーザー分析ツール
公開したランディングページの効果を測定・分析するためのツールです。
まずGoogle Analytics(GA)は必須とも言える一般的な解析ツールで、ページビュー数や直帰率、コンバージョン数など基本指標を把握できます。GAを設定しておけば、流入経路ごとのCVR比較やユーザー属性の分析なども可能です。
またヒートマップツールとしてはミエルカヒートマップやSiTestが挙げられます。ヒートマップではユーザーがページ上のどこをクリックしたか、どこまでスクロールしたかといった行動データを可視化でき、ランディングページのボトルネック発見に役立ちます。

これらのツールを併用することで定量・定性両面からユーザー行動を分析し、次回以降の改善施策に活かせます。また、フォーム最適化にはフォーム専用の解析ツールや、フォーム作成に特化したサービス(Googleフォーム、Typeform等)も便利です。
SEO対策ツール
ランディングページは、広告流入がメインであればSEOは重視しないケースも多いですが、サイト内にランディングページを多数作成して資産化する場合や、サイト型LPで検索流入を狙う場合にはSEOツールも活用しましょう。
代表的なものにAhrefsやSemrushがあります。これらは競合サイトのキーワード分析や被リンク状況の調査ができる、SEO業界定番のツールです。例えば競合がどんな検索キーワードでトラフィックを集めているか、どのサイトからリンクを獲得しているかといった情報を把握でき、自社LPのコンテンツ戦略に役立てられます。料金はかかりますが、本格的にSEO施策を行うなら導入を検討するとよいでしょう。
加えて、Google Search Console(GSC)も必須です。GSCでは自サイトの検索結果での表示回数やクリック数、クエリ(検索語)ごとの順位などを詳しく把握でき、SEOを実施する上で無くてはならないツールです。
ランディングページが検索流入を獲得している場合はGSCで実績を確認し、タイトルやディスクリプションの改善に活かすことも可能です。
以上のようなツールを駆使して、ランディングページの制作効率アップ・効果測定・SEO最適化まで一気通貫で取り組みましょう。
ランディングページ改善のためのチェックリスト
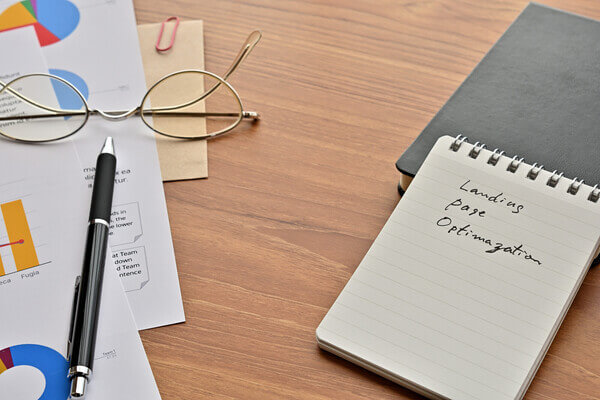
✓CTAは適切に配置されているか?
ボタンが埋もれていないか、文言が行動をうながす表現になっているかをチェックします。矢印や色のコントラストなどを用いて、意識的に目立たせる工夫も重要です。
✓フォームは最小限の入力項目に抑えられているか?
項目が多すぎると、ユーザーは入力の途中で離脱しがちです。本当に必要な情報だけに限定できないか再考し、ステップ分割が必要なら案内をわかりやすくしましょう。
✓見出しやコピーは興味を引く内容になっているか?
見出しやキャッチコピーに数字や問いかけを盛り込み、ユーザーの関心をつかめているか確認します。メリットや価値が具体的に伝わるよう意識しましょう。
✓信頼できる要素が十分に示されているか?
導入実績や顧客の声、第三者評価などの根拠をしっかり提示し、安心感を高めているかを点検します。アイコンやロゴなど視覚的な補強も効果的です。
✓ページの読み込み速度は高速化されているか?
画像の圧縮やスクリプトの軽量化を行い、ユーザーの離脱を防いでいるか確認します。サイト表示速度が低いとSEOや広告効果にも悪影響が及ぶ可能性があります。
✓モバイルでの操作性は最適化されているか?
スマートフォンやタブレットでもレイアウトが崩れず、ボタンや文字が押しやすい大きさになっているかを検証します。レスポンシブ対応やタップのしやすさに配慮しましょう。
✓離脱ポイントは分析されているか?
Google Analyticsやヒートマップツールでページのどこでユーザーが離脱しているかを把握し、原因を推測して改善案を検討します。ファーストビューや中間セクションに焦点を当てると効果的です。
✓広告とランディングページのメッセージは整合性が取れているか?
広告文やバナーで期待させた内容とランディングページの訴求ポイントが一致しているかを見直します。違う印象を与えてしまうと信頼度が下がり、直帰率が高くなる恐れがあります。
✓サンクスメッセージはユーザーを納得させる内容になっているか?
フォーム送信後や購入完了後のページ(サンクスページ)で、次のステップやお礼をきちんと伝えているか点検します。案内や追加情報を準備して、ユーザー体験を最後までサポートしましょう。
✓コンバージョン計測は正しく設定されているか?
Google Analyticsや広告プラットフォームのコンバージョンタグが正確に動作しているか確かめます。タグの誤設定や重複発火がないか、公開後にも定期的にチェックしてください。
✓過剰な装飾や要素は省かれているか?
イラストや動画などを盛り込みすぎると、ページが重くなり離脱に繋がる可能性があります。必要最小限の要素でメッセージを分かりやすく伝えられているか見直しましょう。
✓ランディングページ全体の配色・統一感は保たれているか?
全体のカラーコンセプトやフォントスタイルを統一し、ブランドイメージを崩さないようにします。見づらい文字色やチカチカする配色は避け、読みやすさを重視しましょう。
✓誤字脱字や文法ミスはチェックされているか?
文章に誤字・脱字があると、信頼性を損ねる恐れがあります。複数人での校正やツールを使ったチェックを徹底し、細部まで確認しましょう。
✓ページ上部のナビゲーションは最小限に絞られているか?
ユーザーが他のページへ移動しすぎないよう、外部リンクやサイト内メニューを最小限に抑えます。ランディングページのゴールに集中してもらえる環境を整えることが大切です。
✓ユーザーに合ったページ長さになっているか?
商品単価やターゲット層によって、長めに詳しい説明を求めるケースもあれば、短く簡潔なほうが好まれる場合もあります。離脱率データを見ながら最適なページ長さを検討しましょう。
✓動画やアニメーションは適切な長さと形式になっているか?
動画を埋め込む場合は自動再生を避けるなど、ページ閲覧の邪魔にならない工夫が必要です。データ容量にも気を配り、ページ表示の遅延を防ぎましょう。
✓注意事項や利用規約は十分に明記されているか?
購入や申し込みの際にトラブルを防ぐため、返金ポリシーや重要な法的情報を確認しやすい位置に配置します。ユーザーが不安を感じないための配慮が不可欠です。
✓複数のCTAを設置しているか?
長いランディングページではスクロール地点ごとにCTAを繰り返し表示し、いつでも行動できる状態を作るのが鉄板です。上部だけでなく中段や下部にもボタンを配置しましょう。
✓問い合わせやサポートへの導線は確保されているか?
ランディングページを見てさらに質問があるユーザー向けに、問い合わせフォームやチャットサポートなどを用意しておくと安心感を高められます。連絡先やサポート情報をわかりやすく示しましょう。
✓見込み客への再アプローチ手段は準備されているか?
リターゲティング広告やメールマガジン登録など、離脱したユーザーに再度アプローチできる仕組みがあると成約率向上に役立ちます。Cookie同意を含め、プライバシーへの配慮も忘れずに。
✓メタ情報(titleタグやmeta description)は最適化されているか?
検索結果で表示されるページタイトルや説明文が魅力的かどうかもチェックします。SNSシェア時のOGP設定など細部まで詰めると、より広いユーザー層にアピールできます。
✓エラーページやリンク切れはないか?
間違ったURLや404エラーがあるとユーザー体験を損ない、信頼度が下がります。リンク切れチェックツールなどを活用し、スムーズに閲覧できる状態を保ちましょう。
✓SNSや外部メディアとの連携は考慮されているか?
SNSシェアボタンを配置したり、関連するメディアとの相互リンクを用意したりすると、ランディングページへの流入機会が増加します。どのチャネルから訪れても内容が整合しているか確認しましょう。
✓競合他社のランディングページを研究し、改善案を取り入れているか?
競合が行っている工夫や最新のマーケティング手法をリサーチし、自社のランディングページに活かせる部分を取り入れます。自社独自の強みを打ち出しつつ、常にアップデートを心がけましょう。
まとめ
ランディングページ(LP)は、ターゲットを絞り、明確な訴求と強力なCTAでコンバージョンを最大化させるマーケティング施策の要です。制作フローでは、目的・ターゲット定義→ワイヤーフレーム設計→コンテンツ・デザイン制作→実装→公開後の改善という順序を徹底し、運用段階ではアクセス解析やABテストを駆使して継続的なブラッシュアップを行うことが重要となります。小さな修正が大きな成果につながることも多く、失敗と学びを繰り返す過程でランディングページの完成度が高まります。
加えて、レスポンシブ対応やフォーム最適化、複数流入チャネルとの整合性(広告文やSNS投稿内容とランディングページの訴求を一致させること)にも意識を払うと、ユーザー体験が向上し成果がさらに高まります。ビジネスゴールを明確にしつつ、ユーザーの視点を考慮して、着実にPDCAを回してください。以上の知見をもとに、ランディングページの制作・改善に挑戦してみましょう。
株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。LPOやABテストの実施や施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら
以下のお役立ち資料もぜひダウンロードください。