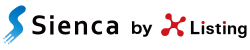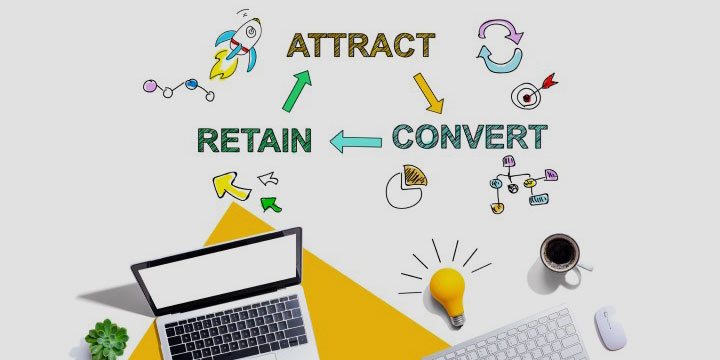3C分析とは?やり方やテンプレート、実際の分析例を紹介
市場環境を把握するための3C分析をすれば、自社を取り巻く環境を整理し、成功につながるヒントを得られることがあります。しかし、「何から手を付ければいいのか分からない」「難しそう」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回、初めて3C分析に取り組む方でも理解できるよう、3C分析の基本から具体的なやり方や役立つテンプレート、さらには実際の企業事例までわかりやすく解説します。自社の現状と課題を明確にし、効果的なマーケティング戦略を立案するためにお役立てください。
3C分析とは市場環境の分析に適したフレームワークのこと

3C分析は、市場環境を総合的に理解し、戦略立案に役立てるためのフレームワークです。市場を取り巻く主要な3つの要素「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合他社)」「Company(自社)」を分析し、自社製品やサービスを取り巻く外部環境と内部環境の相互関係を把握するために役立ちます。
具体的には、以下の3つの視点から3C分析をします。
| 要素 | 意味 | 分析内容 |
| Customer | 市場・顧客 | 市場規模 成長率 トレンド 顧客ニーズ 購買行動など |
| Competitor | 競合他社 | 競合の数 市場シェア 強み・弱み 戦略 製品・サービス 財務状況など |
| Company | 自社 | 経営資源(人・モノ・金・情報) 技術力 ブランド力 強み・弱みなど |
これらの要素を個別に分析するだけでなく、「顧客ニーズに対して自社と競合はどのように対応しているか」などの関連性を考えることが重要です。そこでまずは3C分析の全体像を理解するために役立つ、以下の基礎知識を解説します。
- 3C分析の目的
- 3C分析とPEST分析・4P分析・4C分析の違い
次の項目から、上記2つの基礎知識を順に見ていきましょう。
3C分析の目的
3C分析の最大の目的は、市場における成功要因(KSF:Key Success Factor)を発見し、競争優位性の高いマーケティング戦略を立案することです。
KSFとは、その業界や市場で成功するために最も重要な要素や能力のことです。3C分析を通じて、市場のニーズや、競合の戦略や強み・弱み、そして自社のリソースや能力を総合的に理解することで、「この市場で勝つためには何が重要か」「自社の強みをどう活かすべきか」といったKSFを特定できます。
KSFに基づいた戦略は、客観的な分析に基づくため、成功の可能性が高まります。マーケティング戦略立案のフローにおいて、3C分析は通常、初期段階である「環境分析」フェーズで行われます。
| マーケティング戦略立案フロー | 3C分析の位置づけ |
| 1.環境分析 | 3C分析(市場・顧客、競合、自社)やPEST分析などで、外部環境(機会・脅威)と内部環境(強み・弱み)を客観的に分析する |
| 2.基本戦略の策定 | 環境分析で得られた情報をもとに、ターゲット市場の選定、提供価値の定義(STP分析など)を行う |
| 3.具体的な施策の検討 | 基本戦略に基づき、製品・サービス、価格、プロモーション、流通チャネルなど、具体的なマーケティングミックス(4P/4C分析など)を検討・実行する |
| 4.実行と評価 | 施策を実行し、効果を測定し、必要に応じて改善する |
このように3C分析は、戦略立案の出発点として、現状を正しく認識するために役立ちます。
3C分析とPEST分析・4P分析・4C分析の違い
3C分析は「環境分析」に特化したフレームワークであり、他の分析手法とは目的や対象が異なります。
| 分析手法 | 分析対象 | 主な目的 | 位置づけ |
| 3C分析 | Customer(市場・顧客) Competitor(競合他社) Company(自社) | 市場における成功要因(KSF)の発見 競争優位性の特定 戦略立案の基礎 | 環境分析(外部・内部) |
| PEST分析 | Politics(政治) Economy(経済) Society(社会) Technology(技術) | 市場全体に影響を与える外部要因の特定 将来的な機会や脅威の予測 | 環境分析(外部マクロ) |
| 4P分析 | Product(製品) Price(価格) Place(流通) Promotion(プロモーション) | 自社が顧客に対してどのように価値を提供し、販売するかという施策の検討 | 具体的な施策検討(売り手視点) |
| 4C分析 | Customer Value(顧客価値) Cost(顧客が負担する費用) Convenience(入手容易性) Communication(顧客とのコミュニケーション) | 顧客視点から見たマーケティング施策の検討 顧客満足度の向上 | 具体的な施策検討(買い手視点) |
3C分析は、市場・競合・自社の3つの視点から「外部環境」と「内部環境」を総合的に理解することに主眼を置いています。これに対し、PEST分析は主に「マクロな外部環境」、4P/4C分析は「具体的なマーケティング施策」に焦点を当てています。
これらのフレームワークはそれぞれ異なる役割を持っていますが、組み合わせて活用することで、より網羅的で精度の高い分析と戦略立案が可能になります。例えば、PEST分析でマクロな市場トレンドを把握した上で3C分析を行い、戦略を立案したら4P/4C分析で具体的な実行計画に落とし込む、といった流れが一般的です。
3C分析のやり方・手順
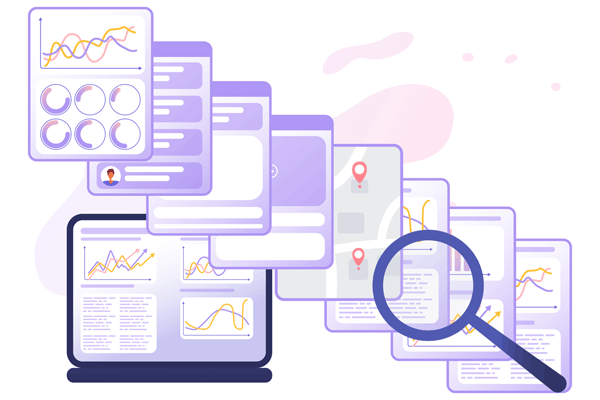
ここでは3C分析を実際にどのように進めるのか、具体的なステップを解説します。分析対象であるCustomer(市場・顧客)・Competitor(競合他社)・Company(自社)の順に、それぞれどのような項目を分析し、どのような視点を持つべきかを見ていきましょう。この手順を踏むことで、抜け漏れなく、かつ戦略立案につながる質の高い分析が可能になります。
Customer(市場・顧客)の分析
3C分析では、まず自社を取り巻く市場と顧客を深く理解することが出発点となります。
顧客ニーズや市場トレンドを正確に把握しなければ、どんなに優れた製品やサービスを持っていても、的外れな戦略になってしまうためです。市場と顧客を正しく理解することで、自社がどこで勝負すべきか、顧客にどのような価値を提供すべきかの方向性が見えてきます。
このフェーズでは、以下の具体的な分析項目に焦点を当てます。
| 分析項目 | 具体的な内容 | 活用できる分析手法 |
| 市場規模・成長性 | 現在の市場規模 過去の推移 将来的な成長予測 市場の成熟度(導入期、成長期、成熟期、衰退期)など | PEST分析 統計データ 業界レポートなど |
| 市場構造 | 参入障壁の高さ 退出障壁の高さ 代替品の脅威 買い手の交渉力 売り手の交渉力など | 5フォース分析など |
| 顧客ニーズ | 顧客が製品・サービスに求める価値 解決したい課題 潜在的なニーズ 購買決定要因(価格・品質・機能・ブランド・サポートなど)など | 顧客アンケート インタビュー 市場調査データ SNS分析 カスタマーサポートへの問い合わせ内容分析など |
| 顧客属性・行動 | 年齢・性別・居住地・職業・所得など ライフスタイル・価値観 購買プロセス(認知→検討→購入→利用) 情報収集チャネルなど | 顧客データ分析 ウェブサイトアクセス解析 購買履歴分析ペルソナ設定など |
| 市場トレンド | 技術トレンド 社会トレンド 法規制の変化 競合の新しい動きなど | PEST分析 業界ニュース 専門レポート カンファレンス情報など |
このCustomer分析においては、マクロな視点とミクロな視点の両方からアプローチすることが効果的です。
PEST分析によるマクロ環境分析
PEST分析は、自社を取り巻くマクロな外部環境を把握するために有効なフレームワークです。
自社や競合の努力だけではコントロールできない、政治・経済・社会・技術といった外部要因の変化は、市場全体や顧客ニーズに大きな影響を与える可能性があるためです。これらの変化を事前に察知すると、将来的な機会や脅威を予測し、3C分析のCustomer分析に深みを与えられます。
PEST分析では、以下の4つの視点から分析を行います。
| 要素 | 意味 | 分析内容例 |
| Politics | 政治 | 法改正 税制変更 規制緩和・強化 政権交代による政策変更 国際情勢など |
| Economy | 経済 | 経済成長率 物価変動 為替レート 金利 雇用情勢 消費者の購買力など |
| Society | 社会 | 人口動態(少子高齢化、都市部への集中) ライフスタイルの変化 価値観の多様化 教育レベル 世論・トレンドなど |
| Technology | 技術 | 新技術の開発・普及(AI・IoT・VRなど) インフラ整備(5Gなど) 研究開発投資の動向 生産技術の進化など |
PEST分析で得られた情報は、Customer分析における「市場トレンド」「顧客ニーズ(変化の兆し)」などを理解する上で役立ちます。例えば、技術の進化(Technology)は新たな顧客ニーズを生み出し、少子高齢化(Society)は市場規模やターゲット層の変化に影響を与えます。これらのマクロな変化を踏まえると、より的確なCustomer分析が可能になります。
5フォース分析によるミクロ環境分析
5フォース分析は、特定の業界や市場における競争要因を分析し、収益性や競争の厳しさを理解するためのフレームワークです。
市場・顧客を分析する上で、その市場が構造的にどのような力学で動いているのか、どのような要因が収益性を左右するのかを理解することは重要です。5フォース分析は、自社の収益性を圧迫する可能性のある5つの要因を明らかにします。
5フォース分析では、以下の5つの要因から競争環境を分析します。
| 要因 | 意味 | 分析内容例 |
| 業界内の競合 | 同じ業界内の企業間の競争 | 競合他社の数と規模・差別化の程度・市場の成長率・固定費の割合・撤退障壁の高さなど 競合が多い、差別化が難しい、市場が停滞しているほど競争は厳しくなる |
| 新規参入の脅威 | 新たに市場に参入してくる企業の脅威 | 参入障壁(規模の経済性、ブランド力、技術、法規制、必要な初期投資など)の高さ 参入障壁が低いほど新規参入の脅威は高まる |
| 代替品の脅威 | 既存の製品やサービスに取って代わる可能性のある製品・サービスの脅威 | 代替品の価格性能比・顧客のスイッチングコスト(乗り換えにかかる費用や手間)・代替品の普及度など 代替品が安価で性能が高く・乗り換えが容易なほど脅威は高まる |
| 買い手の交渉力 | 顧客が価格や品質に対して持つ交渉力 | 買い手の数・購入量・製品・サービスの差別化の程度・スイッチングコスト・買い手にとっての情報量など 買い手の数が少なく、購入量が大きい、製品に差別化がないほど買い手の交渉力は強くなる |
| 売り手の交渉力 | サプライヤー(供給業者)が価格や供給量に対して持つ交渉力 | 売り手の数・供給される製品やサービスの差別化の程度・買い手にとってのスイッチングコスト・売り手にとっての重要度など 売り手の数が少なく、代替が難しいほど売り手の交渉力は強くなる |
これらの5つの要因を分析することで、その市場の魅力度(収益性の高さ)や、自社が直面する競争環境の厳しさを客観的に評価できます。Customer分析で把握した顧客ニーズや市場構造を、この5フォース分析の視点からさらに深掘りすると、より現実的な戦略立案につながります。
5フォース分析ついてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

Competitor(競合他社)の分析
3C分析における競合分析では、単に「競合がいる」ことを把握するだけでなく、彼らの強み・弱み、戦略、市場でのポジションを深く理解することが重要です。
競合他社の状況を正確に把握することで「自社との比較から差別化のポイント」「競合が成功している要因」「失敗している点」を発見できるためです。彼らの動きを予測し、それに対して自社がどのように対応すべきかを検討する上で不可欠なプロセスです。
このフェーズでは、以下の具体的な分析項目に焦点を当てます。
| 分析項目 | 具体的な内容 | 情報収集の方法例 |
| 主要な競合 | 直接的な競合・間接的な競合・潜在的な競合など、自社の製品・サービスが代替される可能性のある企業を特定する | 市場調査 業界レポート 顧客へのヒアリング オンライン検索など |
| 競合の概要 | 企業規模・設立年・従業員数・売上高・利益率・事業内容・主要ターゲット顧客など | 企業HP IR情報 ニュースリリース 業界データサイトなど |
| 製品・サービス | 提供している製品・サービスの種類・特徴・品質・価格帯・ラインナップ・技術レベルなど | 競合のウェブサイト カタログ 製品レビュー 実際にサービスを利用してみるなど |
| マーケティング戦略 | ターゲット顧客・ブランディング・プロモーション手法(広告・SNS・コンテンツマーケティングなど)・販売チャネル・顧客サービスなど | 競合のウェブサイト SNSアカウント 広告クリエイティブ プレスリリース 業界ニュース 顧客の口コミなど |
| 強み・弱み | 技術力・ブランド力・顧客基盤・販売チャネル・コスト構造・組織文化・資金力など、競合が持つ相対的な優位性や劣位性 | 上記の各分析項目から総合的に判断 業界レポート 競合の採用情報(求める人材から強みを推測) 顧客からの評判など |
| 市場でのポジショニング | 市場全体の中で競合がどのような顧客層をターゲットにし、どのような価値を提供することで差別化を図っているか | 競合のメッセージ ウェブサイトのデザイン ターゲット顧客層の分析 顧客レビューなど |
| 最近の動向 | 新規事業への参入・提携・M&A・人員増減・技術開発の状況・資金調達など、競合の戦略的な動き | ニュースリリース 業界ニュース 専門媒体 SNSなど |
競合分析を行う際は、複数の競合を比較分析することが重要です。特に、市場シェアの高い主要な競合だけでなく、新しいビジネスモデルで急成長している競合など、異なるタイプの競合を分析すると、より多角的な視点が得られます。競合の「成功している点」と「課題と思われる点」の両方を客観的に捉えるようにしましょう。
Company(自社)の分析
3C分析の最後のステップは、自社自身を客観的に分析することです。市場や競合をどれだけ正確に分析しても、自社の能力やリソースを正しく理解していなければ、実現不可能な戦略を立ててしまったり、自社の強みを活かせなかったりするからです。
自社の強みや弱み、そして保有する経営資源を明確にすることで、市場の機会を捉え、競合に対して優位に立つための戦略が見えてきます。このフェーズでは、以下の具体的な分析項目に焦点を当てます。
| 分析項目 | 具体的な内容 | 情報収集の方法例 |
| 経営資源 | 人材(従業員のスキル・経験・モチベーション)・資金(財務状況、投資余力)・物(設備・特許・ブランド・顧客リスト)・情報(顧客データ・ノウハウ)など | 財務諸表 組織図 人事データ 資産リスト 顧客データベース 社内アンケートなど |
| 事業内容・強み | 現在提供している製品・サービス・得意とする技術・独自のノウハウ・ブランド力・顧客からの信頼・コスト競争力・組織力など | 社員へのヒアリング 顧客アンケート 営業データ 製品・サービスの評価 過去の成功事例など |
| 弱み・課題 | 資金不足・人材不足・技術の陳腐化・ブランド認知度の低さ・販売チャネルの弱さ・非効率な業務プロセスなど、競争において不利になる可能性のある点 | 社内会議での議論 従業員アンケート 顧客からのクレーム 競合との比較 業務フロー分析など |
| 企業文化・ビジョン | 企業の価値観・行動規範・目指す方向性など。戦略の実行可能性や従業員のモチベーションに影響を与える | 経営理念 社史 従業員へのヒアリング 社内イベントの内容など |
| 収益構造 | どのような製品・サービスで、どの顧客層から、どのように収益を上げているか | 損益計算書 製品別・顧客別の売上 データ価格戦略など |
自社分析においては、特に「強み」と「弱み」を洗い出すことが重要です。自社の強みは、市場の機会を捉え、競合に対して差別化を図る上で核となります。一方、弱みは、戦略実行上のボトルネックとなったり、競合に突かれるポイントになったりする可能性があるため、認識し、対策を講じる必要があります。
VRIO分析による競合優位性分析
VRIO分析は、自社が持つ「経営資源」や「組織能力」が、持続的な競争優位性の源泉となりうるかを評価するためのフレームワークです。
自社の「強み」をさらに深掘りし、それが単なる一時的な優位性ではなく、長期的に競争に勝ち続けるための基盤となりうるのかを見極めるために役立ちます。VRIO分析を行うことで、真に価値ある自社の強みを発見できます。
VRIO分析では、自社の経営資源や組織能力を以下の4つの視点から評価します。
| 評価視点 | 意味 | 判断基準 |
| Value(経済価値) | その経営資源や組織能力は、市場の機会を捉え、脅威を回避するために価値があるかを把握する | 顧客ニーズを満たしているか? コスト削減や収益増加に貢献するか?など |
| Rarity(希少性) | その経営資源や組織能力は、競合他社が保有していない、あるいは容易に真似できない希少なものかを把握する | 競合は同じものを持っているか? 簡単に手に入れられるか?など |
| Imitability(模倣可能性) | その経営資源や組織能力は、競合他社が模倣することが難しいかを把握する | 模倣するためのコストや時間がかかるか? どのようにして生まれたのかが分かりづらいか? |
| Organization(組織) | その経営資源や組織能力を、組織として最大限に活用できる体制になっているかを把握する | それを活かすための組織構造・マネジメントシステム・報酬制度などが整っているか? 従業員がその価値を理解し、活用しようとしているか? |
この4つの問いに対して「Yes」と答えられる項目が多いほど、それは持続的な競争優位性の源泉となりうる可能性が高いと言えます。VRIO分析を通じて、自社の真の強みを見つけ出し、それを活かす戦略を立案することが、Company分析の重要なゴールの一つです。
効果的な3C分析を行う4つのコツ
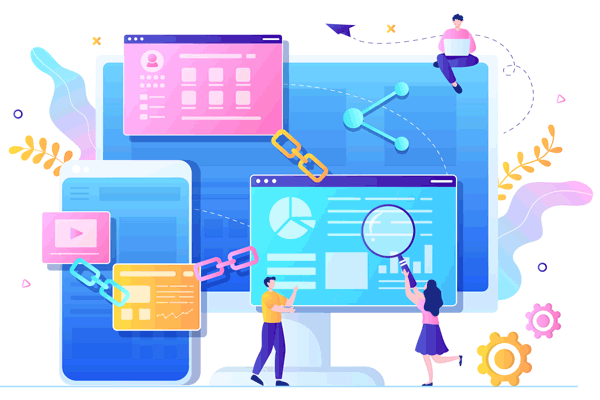
このセクションでは、3C分析をより実践的で、意味のあるものにするための4つの重要なコツをご紹介します。これらのポイントを押さえることで、分析結果が単なる情報の羅列に終わらず、具体的な戦略策定につながる洞察を得やすくなります。
3C分析では事実だけを情報として集める
3C分析をする際は、主観や先入観を排除し、客観的な事実のみを情報として収集することが大切です。分析の初期段階で憶測や願望、個人的な意見に基づいて情報を集めると分析結果の正確性が下がり、誤った現状認識や戦略立案につながるリスクがあるためです。
例えば「うちの製品は競合より優れているはずだ」「顧客はきっとこれを求めているだろう」といった思い込みは正確な分析を妨げます。事実に基づいた情報を収集するためには、以下のような点に注意しましょう。
| 注意点 | 詳細 |
| 一次情報と二次情報を区別する | 一次情報:自社で直接収集した情報(顧客アンケート、営業報告、社内データ、従業員へのヒアリングなど) 二次情報:外部の調査機関やメディアが発表した情報(市場レポート、統計データ、ニュース記事、競合の公開情報など) ※一次情報は自社の独自の視点からの情報として、二次情報は業界全体の動向や客観的なデータとして、それぞれ重要。特に一次情報は自社にしかない貴重な情報源となる。 |
| 情報の出所を確認する | データの信頼性や偏りがないかを確認する。可能な限り複数の情報源から情報を収集し、クロスチェックすることが望ましい。 |
| 定量情報と定性情報の両方を集める | 定量情報:数値で表せる客観的なデータ(市場規模、売上高、顧客数、ウェブサイトのアクセスデータなど) 定性情報:数値では表せない、顧客の意見や行動、競合の戦略の背景など(顧客の声、従業員の意見、ニュース記事の論調など) ※定量情報で客観的な事実を把握し、定性情報でその背景にある理由やニュアンスを理解することで、より深い洞察が得られる。 |
事実に基づいた情報収集は、その後の分析の質を大きく左右します。先入観を捨て、客観的な視点で情報を集めることを心がけましょう。
自社にしかない一次情報を集める
3C分析の質を高めるためには、外部にはない、自社独自の一次情報を積極的に集めることが有効です。
公開されている二次情報は、競合他社も容易に入手できます。しかし自社の顧客から直接聞いた声、営業担当者が現場で感じたこと、カスタマーサポートに寄せられる問い合わせ内容は、「自社にしかない」貴重な情報源となります。
これらの一次情報には、市場の隠れたニーズや競合の知られていない弱点、自社の真の強みといった、戦略策定に直結する重要なヒントが含まれている可能性が高いです。自社にしかない一次情報を集めるための具体的な方法としては、以下が挙げられます。
| 収集方法 | 収集できる情報の内容 |
| 顧客アンケートやインタビュー | 製品・サービスの利用状況、満足度、改善要望、競合の評価など |
| 営業担当者からのヒアリング | 顧客との商談で得られた情報、市場の反応、競合の動きに関する生の声 |
| カスタマーサポートへの問い合わせ内容分析 | 顧客がどのような点に困っているのか、どのような疑問を持っているのか |
| ウェブサイトのアクセス解析 | 顧客がどのような経路でサイトに訪れ、どのようなコンテンツに関心を持っているのか |
| 社内各部署からの情報収集 | 開発、製造、マーケティングなど、各部署が持つ専門的な知見や現場の情報 |
これらの一次情報は、市場や競合の表面的な情報だけでは見えてこない、より深い洞察を与えてくれます。特に顧客の「生の声」は、潜在的なニーズや不満を捉える上で非常に重要です。
現場や顧客の声なども積極的に取り入れる
3C分析においては、データやレポートだけでなく、現場で働く従業員の声や、実際に製品・サービスを利用している顧客の声など、定性的な情報も積極的に取り入れるとよいでしょう。数字や統計データだけでは捉えきれない、市場や顧客の感情、雰囲気、そして現場のリアルな状況を理解するためです。
例えば、データ上は問題なくても、現場の従業員が特定の業務に非効率さを感じていたり、顧客が言葉にはしない不満を抱えていたりする場合があります。これらの生の声は、分析の解像度を上げ、より実践的な戦略につながります。現場や顧客の声を取り入れる方法として、以下をご参考ください。
| 収集方法 | 収集できる情報の内容 |
| 従業員へのヒアリングやワークショップ | 部署横断での意見交換、現場の課題やアイデア |
| 覆面調査(ミステリーショッパー) | 顧客視点での競合店舗やサービスの強み・弱み |
| ソーシャルリスニング | SNSや口コミサイトで、自社や競合、業界全体に対する顧客の評判や意見 |
| 営業同行やカスタマーサポートの応対モニタリング | 実際の顧客とのやり取りを通じて、顧客のリアルな反応や課題 |
これらの定性的な情報は、定量的なデータだけでは見えない「なぜ」を明らかにする手助けとなります。「データは語るが、現場は呻く」という言葉もあるように、現場や顧客の生の声に耳を傾けることで、より実態に即した、示唆に富む3C分析が可能になります。
BtoB業界の場合、顧客業界も含めた6C分析が必要
6C分析とは、主にBtoB(企業間取引)ビジネスにおいて、自社を取り巻く環境だけでなく、取引先である顧客企業を取り巻く環境も分析するフレームワークです。
BtoBビジネスでは、自社の製品やサービスが顧客企業のビジネス成功に貢献することで、自社の成功も達成されるという構造があります。そのため、自社側のCustomer(顧客)、Competitor(競合他社)、Company(自社)の3Cだけでなく、顧客企業側のCustomer(顧客の顧客)、Competitor(顧客の競合)、Company(顧客の会社)という視点も加えると、分析の質を高められると考えられます。顧客企業のビジネス環境や課題を深く理解することで、より的確な提案や戦略立案が可能になるでしょう。
| Cの名称 | 対象 | 内容 |
| Customer(顧客) | 自社の顧客 | 自社が取引する顧客(企業)のニーズや特性 |
| Competitor(競合他社) | 自社の競合 | 自社と競合する他社の動向・強み・弱み |
| Company(自社) | 自社 | 自社の強み・弱み・事業環境 |
| Customer`s Customer(顧客の顧客) | 顧客企業の顧客 | 顧客企業がサービス・製品を提供する先のニーズや特性 |
| Customer`s Competitor(顧客の競合) | 顧客企業の競合 | 顧客企業と競合する他社の動向 |
| Company(顧客の会社) | 顧客企業 | 顧客企業自身の強み・弱み・事業環境 |
6C分析をすると、単に自社製品・サービスを販売するだけでなく、顧客企業がどのような市場で、どのような競合と戦い、最終的にどのような顧客に価値を提供しているのかを把握しやすくなります。例えば、自社が部品メーカーであれば、部品を納入する完成品メーカー(自社のCustomer)だけでなく、その完成品メーカーがどのような製品を開発し(顧客企業のCompany)、どのような競合(顧客企業のCompetitor)と競争し、最終的にどのような消費者(顧客企業のCustomer)に販売しているのかを理解することが重要です。
顧客企業の3Cを深く理解することで、自社が提供する部品が、顧客企業の製品を通じて最終顧客にどのような価値をもたらすかを考慮した、より戦略的な提案や製品開発が可能になります。
今すぐ使える!3C分析のテンプレート
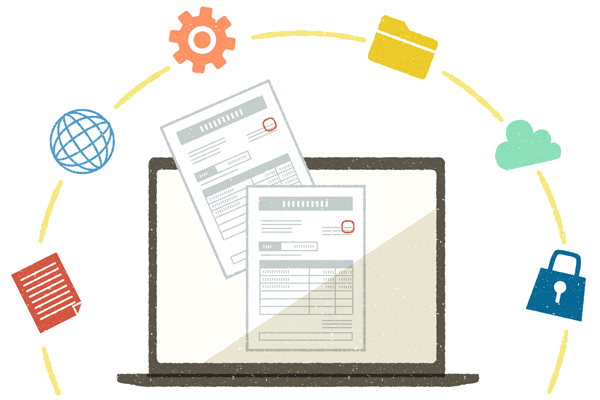
このセクションでは、これまでの解説を踏まえて、実際に3C分析を行う際に役立つテンプレートをご紹介します。テンプレートを活用することで、分析項目を網羅し、情報を整理しやすくなります。
3C分析で洗い出すべき項目は多岐にわたるため、テンプレートがないと情報の抜け漏れが発生したり、分析の視点が偏ったりする可能性があります。テンプレートは、Customer・Competitor・Companyの各要素について、どのような情報を集め、整理すれば良いのかを明確に示してくれるため、分析プロセスをスムーズに進めることができます。
以下に、3C分析の基本的なテンプレートのイメージを示します。このテンプレートを参考に、自社の状況や分析目的に合わせて項目を調整してご活用ください。
| 分析要素 | 分析項目 | 詳細 | 結果から得られる情報 |
| Customer (市場・顧客) | 市場規模・成長性 | 市場規模 成長率 トレンドなど | 市場の魅力度、参入・撤退の判断、成長戦略の方向性 |
| 市場構造 | 参入障壁 代替品の脅威 交渉力など | 競争環境の厳しさ、収益性への影響 | |
| 顧客ニーズ・行動 | 顧客属性 購買決定要因 潜在ニーズなど | ターゲット顧客の明確化、提供すべき価値、製品・サービス開発のヒント | |
| Competitor (競合他社) | 主要競合 | 企業名 概要など | ベンチマーク対象の特定 |
| 製品・サービス | 特徴 価格 品質など | 競合との差別化ポイント、自社製品・サービスの改善点 | |
| マーケティング戦略 | ターゲット プロモーション 販売チャネルなど | 競合の成功・失敗要因、自社の取るべき戦略 | |
| 強み・弱み | 技術力 ブランド力 コスト構造など | 自社の相対的な優位性・劣位性、対策の必要性 | |
| Company (自社) | 経営資源 | 人材 資金 設備情報など | 自社の能力で実現可能な戦略、必要なリソース |
| 事業内容・強み | 得意技術 ブランド力 顧客基盤など | 自社の核となる能力、競争優位性の源泉 | |
| 弱み・課題 | 資金不足 人材不足 非効率なプロセスなど | 克服すべき課題、リスク要因 | |
| 総合分析 | KSF(成功要因) | Customer,Competitor,Companyの分析結果から導き出される、市場で成功するために最も重要な要素 | 優先的に注力すべき領域、戦略の方向性 |
| 戦略の方向性 | KSFを踏まえ、自社の強みを活かし、市場の機会を捉えるための具体的な戦略の方向性 | 次のステップ(STP、4P/4Cなど)への橋渡し |
このテンプレートに沿って分析を進めることで、情報を整理し、3Cそれぞれの要素から重要な情報を引き出しやすくなります。
3C分析後のマーケティング戦略立案の流れ
3C分析で現状を把握したら、次のステップとして具体的な戦略立案に進みます。
3C分析だけでは自社の機会や脅威、強みや弱みが明らかになるものの、それらを組み合わせてどのように行動すべきかという具体的な方向性は示されません。分析結果をもとに、自社が取るべき戦略の選択肢を検討し、具体的な施策に落とし込むプロセスが必要です。
一般的なマーケティング戦略立案の流れは、以下をご覧ください。
| ステップ | 主な内容 | 活用されるフレームワーク例 |
| 1.環境分析 | 自社を取り巻く外部環境(市場・顧客、競合、マクロ環境)と内部環境(自社)を客観的に分析し、機会・脅威、強み・弱みを特定する | 3C分析 PEST分析 5フォース分析 VRIO分析など |
| 2.SWOT分析 | 環境分析で収集した情報をもとに、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」を把握し、それらの組み合わせから戦略的な課題や方向性を導き出す | SWOT分析 クロスSWOT分析など |
| 3.基本戦略の策定 | SWOT分析の結果を踏まえ、ターゲット市場の選定、顧客への提供価値の定義、競争優位性の源泉などを明確にする | STP分析(Segmentation,Targeting,Positioning) 差別化戦略 コストリーダーシップ戦略など |
| 4.具体的な施策の検討 | 基本戦略に基づき、製品・サービス、価格、流通、プロモーション、KPIなど、具体的なマーケティングミックスを計画する | 4P分析(Product,Price,Place,Promotion) 4C分析(Customer Value,Cost,Convenience,Communication) |
| 5.実行と評価 | 計画した施策を実行し、効果測定を行い、必要に応じて改善を繰り返す | KPI設定 効果測定ツール PDCAサイクルなど |
この流れの中でも、特に3C分析で得られた分析結果を、具体的な戦略に結びつけるために重要な役割を果たすのが「SWOT分析」です。3C分析で洗い出した事実情報を元に、自社の強み・弱み、そして市場の機会・脅威を明確にし、次の戦略ステップへとつなげていきます。
3C分析を具体的施策に落とし込むSWOT分析とは
SWOT分析は、3C分析で明らかになった情報を「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの要素に整理し、自社の現状を総合的に評価するためのフレームワークです。
3C分析で集めたCustomer・Competitor・Companyに関する情報は多岐にわたります。SWOT分析を用いることで、これらの情報を自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)に分類し、戦略的な意味合いを持たせることができます。これにより、自社が直面している状況をシンプルかつ明確に把握し、次に取るべき行動の方向性を見出すことが可能です。
SWOT分析の4つの要素は以下の通りです。
| 要素 | 意味 | 3C分析との関連性 |
| 強み(Strength) | 自社の内部環境における強み(ポジティブ要因) | Company分析で見つかった、競合他社よりも優れている点や、市場の機会を活かせる能力 |
| 弱み(Weakness) | 自社の内部環境における弱み(ネガティブ要因) | Company分析で見つかった、競合他社よりも劣っている点や、市場の機会を活かす上で障害となる点 |
| 機会(Opportunity) | 外部環境における機会(ポジティブ要因) | Customer分析やCompetitor分析、PEST分析で見つかった、自社にとって有利に働きうる市場の動向や変化、競合の弱点など |
| 脅威(Threat) | 外部環境における脅威(ネガティブ要因) | Customer分析やCompetitor分析、PEST分析で見つかった、自社にとって不利に働きうる市場の動向や変化、競合の強み、法規制の変更など |
なおSWOT分析をさらに発展させたものに「クロスSWOT分析」があります。これは、4つの要素をそれぞれ組み合わせて(強み×機会、強み×脅威、弱み×機会、弱み×脅威)、より具体的な戦略オプションを検討する手法です。
| 組み合わせ | 意味合い | 戦略の方向性例 |
| 強み×機会 | 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用するための戦略 | 積極的に市場に参入する、新製品を投入する、事業を拡大する(攻めの戦略) |
| 強み×脅威 | 自社の強みを活かして、市場の脅威を回避したり、影響を最小限に抑えたりするための戦略 | 競合の攻勢に対抗する、リスクを分散する、自社の優位性をアピールする(差別化戦略) |
| 弱み×機会 | 市場の機会を捉えるために、自社の弱みを克服したり、弱みが影響しないように回避したりするための戦略 | 弱みを補うための提携やM&A、新たな技術導入、業務プロセスの改善(弱点克服戦略) |
| 弱み×脅威 | 市場の脅威による影響を最小限に抑えつつ、自社の弱みが致命的なダメージにつながらないようにするための戦略 | 事業からの撤退、リスクの高い市場からの撤退、コスト削減、事業規模の縮小(防御戦略) |
3C分析で得た客観的な事実をSWOT分析で整理し、さらにクロスSWOT分析で戦略オプションを検討すると、より自社の状況に適した具体的なマーケティング戦略を検討しやすくなります。
3C分析・競合分析にお悩みならツール・支援サービスの活用がおすすめ!
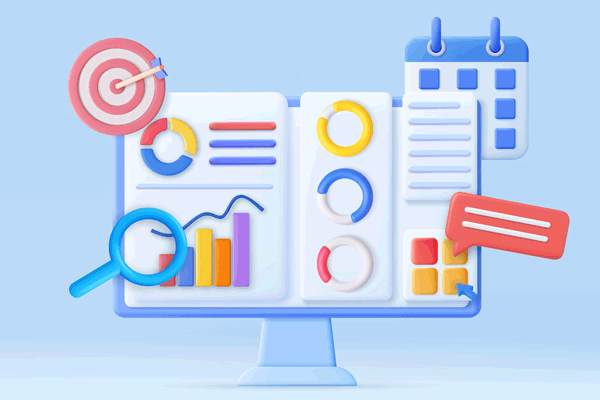
3C分析、特に競合分析を行うのが難しいと感じる場合は、専門の分析ツールを活用するのがおすすめです。
ツールを利用することで、手動では難しい大量のデータ収集や分析を効率的に行えるためです。特にウェブサイトのアクセスデータやユーザー行動に関する情報は、ツールを使わないと正確に把握することが難しいでしょう。
そこで競合のウェブ戦略やユーザー像を明らかにし、自社の分析に深みを与えてくれる3C分析、特に競合分析に役立つツールやサービスをご紹介します。
- Dockpit
- Sienca
CustomerやCompetitorに関する客観的なデータを収集する上で強力な助けとなるので、次の項目から詳細を見ていきましょう。
Dockpit
Dockpitは、競合サイトのアクセス状況やユーザー属性などを詳細に分析できるツールです。
競合サイトの訪問者数、流入経路(検索キーワード、参照サイト、広告など)、ユーザー属性(年齢、性別、興味関心など)、サイト内行動といったデータを把握できるため、競合がどのようなターゲットに、どのような手法でアプローチしているのか、また彼らのサイトがユーザーにどのように利用されているのかを具体的に理解できます。
これは、3C分析におけるCustomer分析(ターゲットユーザーの理解)とCompetitor分析(競合のウェブ戦略理解)に直接的に役立ちます。
Dockpitを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
| メリット | 内容 |
| 競合サイトの集客戦略を把握できる | どのようなキーワードで集客しているか、どの広告媒体を活用しているかなどが分かる |
| 競合サイトのユーザー像を理解できる | 競合サイトに訪れるユーザー層を把握し、自社のターゲット設定と比較検討できる |
| 市場全体のトレンドやユーザー行動を分析できる | 特定の業界やキーワードにおけるユーザーの検索行動や関心事を広く捉えることができる |
| データに基づいた客観的な競合分析が可能になる | 感覚ではなく、具体的な数値データに基づいて競合を評価できる |
これらの情報は、3C分析の精度を高め、より効果的なデジタルマーケティング戦略を立案するために非常に役立ちます。
Sienca
クロスリスティングの提供するマーケティング支援サービス「Sienca」は、3C分析や競合分析を行う上で、以下の理由から非常におすすめと言えます。
| おすすめ理由 | 概要 | 3C分析・競合分析への貢献 |
| 1.3Cの視点を網羅した包括的な分析が可能 | 自社、競合、顧客(市場)という3つの視点からデータに基づいた分析を実施 | Customer(市場・顧客):アクセス解析、ユーザー属性、コンバージョンまでの動きからユーザーニーズや行動パターンを把握 Competitor(競合):指定した競合サイトのアクセス状況、ユーザー属性、ユーザー動線を分析し、競合戦略を具体的に把握 Company(自社):自社サイトのアクセス、ユーザー行動から課題を発見 これらの要素を統合的に分析することで、自社と競合の比較だけでなく、市場や顧客ニーズを踏まえた多角的な3C分析が可能 |
| 2.具体的なデータに基づいた客観的な分析 | 「アクセス解析」「ユーザー属性」「コンバージョンまでのユーザーの動き」といった、数値や事実に基づいた具体的なデータ項目を分析レポートとして提供 | データに基づいた客観的な根拠をもって、競合の強み、自社の弱み、ユーザーの行動パターンを把握できる 特にコンバージョンに至るまでの詳細なユーザー動線を分析することで、顧客がどのように成果につながるのか、あるいはどこで離脱するのかを具体的に理解し、ボトルネックや成功要因を特定可能 感覚や主観に頼らず、事実に基づいた正確な3C分析・競合分析を行い、説得力のある戦略立案につなげられる |
| 3.分析に留まらない、成果につながる施策提案 | 単に現状を分析するだけでなく、その分析結果(自社の課題、競合との比較から見えた差別化ポイントなど)に基づき、「成果につながる施策」を具体的に提案 | 3C分析や競合分析で明らかになった課題や機会に対して、具体的な改善策や次のアクションについて示唆が得られる 分析結果を実際のビジネス戦略やマーケティング施策(広告運用改善、コンテンツ強化、CROなど)に直接活かせる 分析で終わらず、データに基づいた戦略実行や具体的な改善活動につながる、実践的な3C分析・競合分析となる |
| 4.クロスリスティングの信頼性と実績 | 設立20年の豊富な経験と蓄積されたノウハウ、NTTドコモ100%子会社としてのNTTグループの一員という信頼性、デジタルマーケティングのトータルソリューション提供実績がある | 長年の経験と実績に基づいた専門家の知見が加わることで、データ分析だけでは見えにくい本質的な課題発見や、より有効性の高い施策提案につながる可能性がある 信頼できる企業による分析であるため、分析結果の妥当性や提案内容の質が高いと期待できる 分析自体の信頼性が高く、質の高い3C分析・競合分析をサポートし、その後の戦略策定の確度を高められる |
アクセス解析・コンバージョンなどのデータ分析や、成果につながる施策の提案などが可能なSiencaは、3C分析によって目標達成をしたい場合におすすめです。データ収集や分析の専門知識やリソースが社内に不足している場合でも、専門家による質の高い分析と提案を受けられます。
現在当社では、Dockpitを活用し、お客様のサイトとサービス競合にご指定頂いたサイトを比較・分析する、競合分析レポートを無料でご提供しています。3C分析、特に競合分析に課題を感じている場合は、お気軽にお申し込みください。
3C分析フレームワークによる環境分析事例
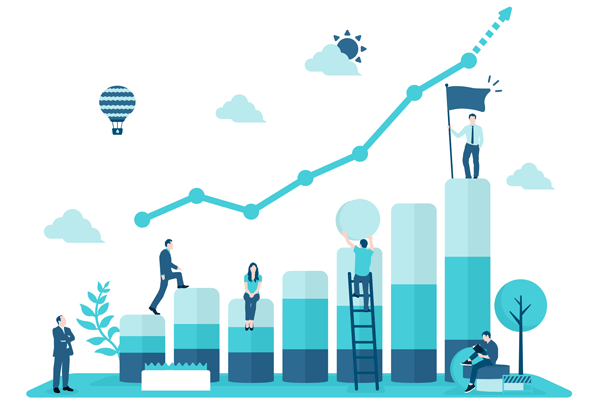
このセクションでは、これまで解説してきた3C分析のフレームワークが、実際の企業でどのように活用され、成功につながっているのかを具体的な事例を通して見ていきます。有名な企業の事例を知ることで、3C分析の活用イメージをより具体的に掴み、自社の分析に応用するためのヒントを得られるはずです。
スターバックスの3C分析事例
スターバックスは、独自の「サードプレイス(第三の場所)」というコンセプトを確立することで、競争の激しいカフェ市場で成功を収めました。これは、優れた3C分析に基づいています。
具体的な分析プロセスと成功要因として、以下が考えられます。
- Customer(市場・顧客):顧客は高品質なコーヒーだけでなく、くつろげる空間やパーソナルなサービスを求めている。単なる休憩場所ではなく、友人との交流や作業、読書などができる「居場所」としてのニーズがあることを発見。
- Competitor(競合他社):多くのカフェ・喫茶店は、短時間で回転率を上げるビジネスモデル。価格競争が中心で、空間の質やサービスの均一性に課題がある場合が多い。
- Company(自社):高品質なアラビカ種コーヒー豆の調達・焙煎能力、マニュアル化されたオペレーションによる品質・サービスレベルの維持、世界観を統一した心地よい店舗デザイン、バリスタの専門性とフレンドリーな接客。
- 分析結果から導き出されたKSF:「高品質なコーヒー」と「居心地の良い空間・体験」の提供。
- 成功要因:このKSFに基づき、「サードプレイス」という独自のポジショニングを確立。高価格帯でありながらも、顧客がその空間と体験に価値を感じることでリピーターを獲得しました。徹底したブランド管理と従業員教育も、このコンセプト実現に不可欠でした。
スターバックスは単にコーヒーを提供するだけでなく、顧客が自宅でも職場でもない、リラックスして過ごせる快適な空間(サードプレイス)を求めているという潜在的なニーズを深く理解しました(Customer分析)。
既存のカフェや喫茶店が価格競争や短時間の滞在を前提としている中(Competitor分析)、スターバックスは高品質なコーヒー、洗練された店舗デザイン、フレンドリーな接客、無料Wi-Fiといった自社の強み(Company分析)を活かす戦略を立てました。
良品計画(無印良品)の3C分析事例
無印良品は、「これでいい」という思想に基づいたシンプルで質の高い製品と、一貫した世界観で独自の地位を築いています。これも綿密な3C分析の賜物と言えます。
具体的な分析プロセスと成功要因は以下の通りと考えられます。
- Customer(市場・顧客):機能的で飽きのこないデザイン、素材感を重視した製品を求める層。ブランド名よりも製品自体の質や哲学に共感する顧客。シンプルで丁寧な暮らしへの志向。
- Competitor(競合他社):アパレル、生活雑貨、食品など多様な業界に競合が存在するが、それぞれが特定のカテゴリやテイストに特化している。無印良品のように幅広いカテゴリで一貫した世界観を持つ競合は少ない。
- Company(自社):「わけあって安い」というコンセプトに基づいた、素材の選定から製造工程の見直しによるコスト削減能力。企画開発から販売まで一貫したSPAモデルによる迅速な商品化と品質管理。一貫した店舗デザインやパッケージによる強いブランドイメージ。「これでいい」という哲学に基づいた製品企画力。
- 分析結果から導き出されたKSF:「シンプルで機能的なデザイン」「高品質な素材」「適正価格」「一貫した世界観」。
- 成功要因:これらのKSFを徹底することで、特定のライフスタイルを提案するブランドとして独自のポジションを確立。広告宣伝に過度に依存せず、製品そのものの力と顧客の共感によって支持を広げています。
無印良品は、過剰な装飾やブランド名に価値を見出すのではなく、素材そのものの良さや機能性、シンプルさを求める顧客層がいることを見抜きました(Customer分析)。
競合他社がブランドイメージや流行を重視する傾向にある中で(Competitor分析)、無印良品は企画開発から製造、物流、販売までを一貫して行うSPA(製造小売業)という自社の強み(Company分析)を活かし、高品質な商品を適正価格で提供するモデルを構築しました。
ユニクロの3C分析事例
ユニクロは、「高品質ベーシックウェア」という独自の市場を創造し、世界的なカジュアルウェアブランドに成長しました。これも3C分析に基づいた戦略実行の成功事例です。
具体的な分析プロセスと成功要因は以下の通りと考えられます。
- Customer(市場・顧客):流行に左右されず、日常的に着られるシンプルで高品質な衣類を手頃な価格で求める幅広い層。快適性や機能性を重視するニーズ。
- Competitor(競合他社):アパレル業界には多様な競合が存在するが、ファストファッションは低価格だが品質に課題がある場合が多く、セレクトショップなどは高品質だが高価格帯。ユニクロのように「高品質ベーシック」を強みとする競合は当時少なかった。
- Company(自社):企画開発から生産、物流、販売までを自社で管理するSPAモデル。東レなどの素材メーカーとの連携による独自の機能性素材(ヒートテック、エアリズムなど)の開発力。大量生産・大量販売によるコスト競争力。グローバルなサプライチェーン管理能力。大型店舗による豊富な品揃えと買いやすい空間。
- 分析結果から導き出されたKSF:「高品質なベーシックウェアを手頃な価格で提供すること」と「独自の機能性素材の開発」。
- 成功要因:これらのKSFを徹底的に追求し、「LifeWear」というコンセプトのもと、機能性とデザイン性を両立したベーシックウェアを提供。SPAモデルによる効率化とコスト削減、そして積極的な海外展開によって規模の経済を活かし、世界的なブランドへと成長しました。
ユニクロは、流行に左右されない、誰でも着られる高品質なベーシックウェアを、手頃な価格で求める顧客層が広く存在することを見抜きました(Customer分析)。
ファッション業界の多くの競合が流行を追い、多品種少量生産で高価格帯の商品を提供する傾向にある中で(Competitor分析)、ユニクロは企画、生産、物流、販売までを自社で一貫して行うSPA(製造小売業)モデルを徹底し、素材開発や大量生産によるコスト競争力、そしてグローバルな物流網といった自社の強み(Company分析)を最大限に活かす戦略を取りました。
これらの事例からも分かるように、3C分析は、単なる分析で終わるのではなく、そこで得られた洞察を基に、自社独自の強みを活かし、市場の機会を捉え、競合に対して差別化を図るための具体的な戦略に結びつけることが重要です。
まとめ
3C分析は、市場環境を客観的に理解し、競争優位性の高い戦略を立案するために役立ちます。変化の激しい現代において、自社の立ち位置を正しく理解し、市場で勝ち抜くための戦略を立てることは、企業の存続と成長につながります。
現在当社では、お客様のサイトとサービス競合にご指定頂いたサイトを比較・分析する、競合分析レポートを無料でご提供しています。3C分析、特に競合分析やデジタルマーケティングにおけるユーザーニーズの分析に課題を感じている場合は、お気軽にお申し込みください。