N1分析®とは?ペルソナ分析との違いやメリット、インタビューのやり方などを解説
現代のマーケティングにおいて、顧客理解は非常に重要です。
以下の背景から、マス向けの画一的なアプローチではなく、一人ひとりの顧客に深く寄り添った施策が求められています。
- 顧客の価値観が多様化している
- 購買行動が複雑になっている
- SNSなどの普及により個人の影響力が増している
このような状況の中、「N1分析®」が注目されています。
N1分析®とは、たった一人の顧客を詳しく分析し、多くの顧客に共通するインサイト(潜在的なニーズや動機)を発見するための手法です。
本記事ではN1分析®について、その基本的な考え方から、従来の分析方法との違い、具体的なやり方を解説します。効果的な実施のコツや実際の活用事例も紹介するので、ぜひN1分析®をマーケティング活動に役立ててください。
N1分析®とは、マーケティングリサーチの手法のひとつ

N1分析®とは、一人(N=1)の顧客を深く掘り下げて分析するマーケティング法です。従来の定量調査のように多数の意見を集計するのではなく、一人を徹底的に理解することに重点を置きます。
この分析では、対象者のデモグラフィック情報だけでなく、以下のような多角的な視点からインサイトを得ることを目指します。
- 行動: どのような製品・サービスを、いつ、どこで、どのように利用しているか
- 思考: 製品・サービスに対する考え方、価値観、悩み、願望
- 感情: 製品・サービスを利用する際の喜び、不満、期待
N1分析®は、ペルソナ作成や顧客体験(CX)向上、プロダクト開発など、幅広いマーケティング活動に活用できます。
ペルソナについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。


N1分析®が今注目されている理由
近年、N1分析®が注目されている背景には、以下のような要因が挙げられます。
| 要因 | 概要 |
| 顧客ニーズの多様化 | 個々の顧客の深いニーズを理解し、様々なニーズに対応 |
| デジタル化の進展 | データだけでは見えない背景理解・行動理由の理解 |
| サブスクリプション拡大 | 顧客一人ひとりのLTV向上のための個別理解の重要性 |
画一的な製品・サービスでは顧客満足度を高めることが難しくなってきており、個々の顧客の深いニーズを理解する必要性が高まっています。また顧客行動のデータが取得しやすくなった一方、データだけでは見えない「なぜそう行動したのか」という、顧客の感情・動機を把握する重要性も増しています。
さらに継続的な利用を促すことで、顧客一人あたりのLTV(Life Time Value、顧客生涯価値)を高める視点も大切です。このような理由から、統計的な傾向だけでなく、特定の個人(N=1)を深く掘り下げて理解するN1分析®が、現代のマーケティングにおいて重要な手法と考えられています。
N1分析®のメリット

N1分析®には、以下のような様々なメリットがあります。
- 顧客の深い理解
- 具体的なインサイトの獲得
- 顧客視点に基づいた戦略立案
- 仮説構築と検証の効率化
一人の顧客(N=1)を徹底的に深掘りし、行動に移した理由・潜在的なニーズなどを把握できれば、マーケティング分析・戦略立案の質を高められます。精度の高い仮説を立てることで、大規模な定量調査などにつなげられる可能性がある点も、N1分析®のメリットです。
N1分析®と従来の分析方法との違い
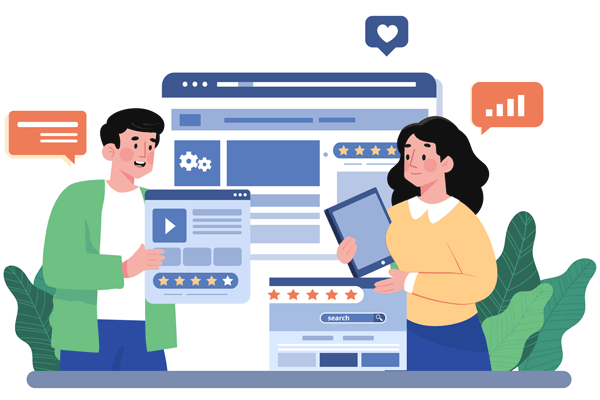
従来の分析方法とN1分析®の違いは、分析の対象や目的などです。
| 項目 | N1分析® | 従来の分析方法 |
| 対象 | 特定の個人(N=1) | 顧客全体 特定のセグメント(N≧多数) |
| 目的 | 個人の深い理解 潜在ニーズの発見 | 全体・セグメントの傾向把握 平均像の理解 |
| 手法 | 質的 ※深層インタビュー、詳細な観察など | 量的 ※アンケート、統計分析など |
| 得られる情報 | 個人の具体的な状況・背景・感情・動機 | 全体的な傾向 数値による客観データ |
従来の分析方法では大量のデータを統計的に処理し、顧客全体や特定のセグメントの平均的な傾向を把握することが一般的で、アンケートなども、回答者全体の傾向を見るために行われることが多いです。
一方、N1分析®は特定の「1人」の顧客(N=1)に深く焦点を当て、その個人の行動・思考・感情・潜在的なニーズなどを徹底的に理解しようとする質的なアプローチです。
なお架空の人物を設定するペルソナ分析と違い、N1分析®は実在する顧客を分析します。
N1分析®のやり方・手順
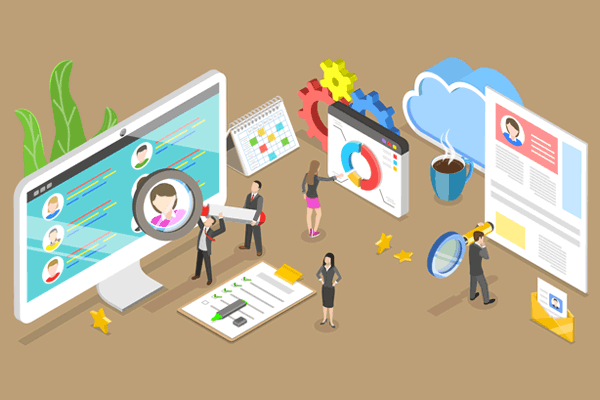
N1分析®を実施する際は、まず5セグマップや9セグマップで顧客をいくつかのセグメントに分類します。次に、各セグメントを代表する個人(N=1)を選び、最後にインタビューやアンケートを用いてその個人に対して深掘り調査を実施します。
このような流れで進めると、深いインサイトを得て、分析の質を高めやすいです。
5セグマップを作成する
N1分析®の最初のステップとして「5セグマップ」での分類があります。5セグマップを活用すればユーザーの行動や意識を把握し、誰を調査対象とするかを明確にできます。
5セグマップでは、主に以下の5つのセグメントにユーザーを分類します。
| 顧客分類 | 認知 | 購買情報 |
| ロイヤル顧客 | 済 | 意欲が高 |
| 一般顧客 | 済 | 意欲は中~低 |
| 離反顧客 | 済 | 現在の購買はないが購買経験あり |
| 認知・未購買顧客 | 済 | 購買経験なし |
| 未認知顧客 | なし | 購買経験なし |
これらのセグメントに分類することで、自社にとって特に深掘りすべきユーザー層を特定できます。例えば「離反顧客」に焦点を当てると、なぜ離反したのか、どのような不満やニーズがあるのかを知る手がかりになります。
9セグマップを作成する
N1分析®の準備段階として作成する「9セグマップ」は、マーケティングにおける顧客の状態を9項目に分類し、自社サービスに対する顧客の現状を明確にするためのフレームワークです。具体的には、以下の2軸で顧客を分類します。
- 横軸:利用・購買経験の有無
- 未利用
- 経験者(離反含む)
- 現利用者
- 縦軸:今後の利用意向
- 消極的
- 中立
- 積極的
上記の方法で、以下の9項目に分類できます。
| 消極的 | 中立 | 積極的 | |
| 未利用 | ① | ② | ③ |
| 経験者 | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 現利用者 | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
このマップを用いると、自社にとって特に重要度の高い顧客層や、アプローチすべき層を視覚的に把握できます。例えば「③未利用で積極的」な層は新規顧客獲得の可能性が高く、「⑨現利用者で積極的」な層はロイヤル顧客として維持・育成すべき対象となります。
調査対象となる個人を選定する
N1分析®では事前に作成したセグマップに基づき、特定のセグメントを代表するような人物を選ぶことが大切です。選定時の重要ポイントは以下のとおりです。
| 選び方 | 詳細 |
| 調査目的との合致 | なぜそのセグメント、その人物を深掘りするのかを明確にする |
| 代表性 | そのセグメントの典型的なニーズ・行動パターンを確認 |
| 情報提供への意欲 | インタビューなど、協力的に詳細な情報を提供してくれるかどうかを検討 |
例えば、新規サービス開発のためにN1分析®をする場合、「特定の課題を強く感じているが、既存サービスでは解決できていない層から選ぶ」などの方法があります。調査目的や典型的なニースなどを把握して、適切な調査対象を選びましょう。
調査対象者に対してアンケートやインタビューを実施する
調査対象者を絞り込んだ後は、実際にアンケートやインタビューを実施します。特に重要なのは、個人の深層心理に迫る対面やオンラインでのインタビューです。
インタビューでは、単に事実を聞き出すだけでなく、対象者の感情や思考プロセスを深く理解することを目指します。以下のような点を意識すると良いでしょう。
| 実施のポイント | 詳細 |
| オープンクエスチョンを活用する | 対象者が自由に答えられる質問をする ※「なぜそう思いましたか?」「具体的にどのような状況ですか?」など |
| 共感的な姿勢で傾聴する | 対象者が安心して本音を話せるよう工夫する ※相槌を打つ・感情に寄り添うなど |
| 非言語情報にも注意を払う | 表情や声のトーン・ジェスチャーなどにも注目する |
インタビュー内容は、録音したりメモを取ったりして、後で詳しく分析できるように準備します。複数人で担当し、多角的な視点から情報を捉えることも有効です。
なおアンケートはインタビュー前のスクリーニングや、インタビューで得た仮説の検証などに活用できます。
効果的なN1分析®を実施するためのコツ

上手くN1分析®を実施するコツは、以下の通りです。
- 調査対象者を深く観察する
- 表面的なニーズではなく、潜在的なニーズを深堀りする
- 分析結果の汎用性を検討する
次の項目から、上記3つの「N1分析®の質を高めるコツ」を見ていきましょう。
調査対象者を深く観察する
以下のような行動・表情・話し方のトーンなど、非言語的な情報に注意するとN1分析®の質を高められます。
- 特定の話題になった時の表情の変化
- 製品・サービスに関する説明を聞いている時の仕草
- 話すスピードや声の大きさの変化
非言語情報に注意すると、本人が意識していない潜在的なニーズや感情、価値観の手がかりを得られることがあります。具体的には「ある機能について話す際に目が輝く」「特定の不満について話す時に声のトーンが下がる」などです。
観察によって得られた情報は、インタビュー内容を補完し、より深い洞察を引き出すための重要な要素となり、インタビューと組み合わせることで、対象者への理解を一層深められるでしょう。
表面的なニーズではなく、潜在的なニーズを深堀りする
N1分析®では、対象者へのインタビューや観察を通じて、単に「何が欲しいか」といった表面的なニーズだけでなく、その背景にある「なぜそれが欲しいのか」「どんな状況でそう感じるのか」といった潜在的なニーズを深掘りすることが非常に重要です。
例えば「もっと効率的に作業したい」というニーズの裏には、以下の潜在的な動機があるかもしれません。
- 時間の節約:プライベートの時間を確保したい
- 疲労の軽減:長時間の作業による身体的負担を減らしたい
- 達成感:短い時間で成果を出したい
これらの潜在的なニーズを把握することで、対象者自身も気づいていないような、より本質的な課題や願望に迫ることができます。これにより、より響く製品・サービスの開発や改善、効果的なコミュニケーション施策の立案につながります。
他にも以下のように、表面的なニーズと潜在的なニーズを整理すると理解が深まります。
| 表面的なニーズ | 潜在的なニーズの例 |
| 操作が簡単なツールが欲しい | ITリテラシーに自信がない 新しいことを覚えるのが億劫など |
| 健康に良い食事がしたい | 病気への不安がある 家族に元気でいてほしいなど |
| 新しい服が欲しい | 自分に自信を持ちたい 周りから良く見られたいなど |
潜在的なニーズの深掘りは、対象者の行動や言動の「なぜ?」を繰り返し問いかけることで可能になります。
分析結果の汎用性を検討する
N1分析®の結果をどのように他の顧客層に応用できるかを検討することも重要です。このような「汎用性」を確認するため、一人の顧客のインサイトが、他の類似した顧客層にも当てはまらないかを見極めましょう。
例えば、インタビューで得られた特定の行動理由や潜在的なニーズが、似た課題や目的を持つ人にも見られないかどうかを見ると、他のマーケティング施策に活かせることがあります。具体的には、以下のように汎用性を評価すると適用範囲を拡大できるかもしれません。
| 汎用性のレベル | 特徴 | 適用範囲の例 |
| 高い | 幅広い顧客層に共通する根源的なニーズ | 多くの顧客が抱える普遍的な課題 |
| 中程度 | 特定のセグメントに共通するニーズ | ペルソナとして設定した層の行動パターン |
| 低い | その個人に固有の特殊なニーズ | 個人的な経験や状況に強く依存するインサイト |
マーケティング施策や製品開発への活用範囲を広げ、より多くの顧客へ価値を提供できるよう、分析結果の汎用性を検討しましょう。
N1分析®を行う際の注意点
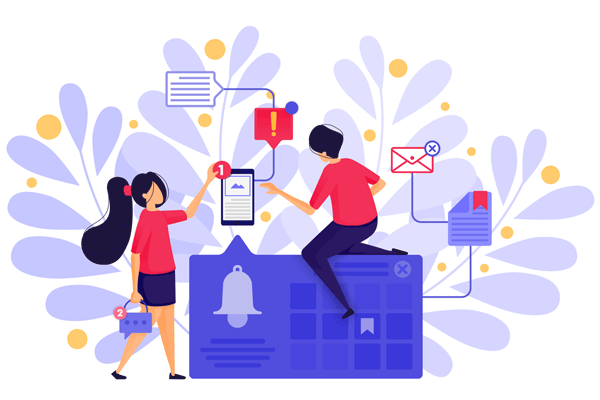
N1分析®は個人の深層ニーズを捉える有効な手法ですが、実施にあたってはいくつかの注意点があります。
| 注意点 | 詳細 |
| 結果の代表性 | N=1の結果が市場全体に当てはまるとは限らない |
| 対象者の選定 | 偏りなく、目的に合った対象者を選ぶことが重要 |
| 担当者のスキル | 質問力・傾聴力・分析力が必要 |
| 定量調査との組み合わせ | 仮説検証や結果の有用性判断のために必須 |
N1分析®は特定の個人(N=1)の深い理解を目指すため、得られたインサイトが普遍的なものなのか、あるいは特定の個人に固有のものなのかを見極める必要があります。また偏った対象者を選ぶと、適切な分析結果が得づらくなる点にも要注意です。
N1分析®の活用事例3選
N1分析®は、様々な企業のマーケティング活動において活用され、成果を上げています。ここでは、代表的な活用事例を3つご紹介します。
- 株式会社LIFULL
- 株式会社AbemaTV(現:株式会社Abema)
- ジンズホールディングス「JINS」
これらの事例から、N1分析®が単なるデータ分析では捉えきれない、顧客の生の声や潜在的なニーズを引き出す強力な手法であることがわかります。
株式会社LIFULLの活用事例
株式会社LIFULLでは、住宅・不動産情報サイト「LIFULL HOME’S」においてN1分析®を活用し、ロイヤル顧客の明確化・ロイヤル化要因の把握に役立ったとしています。データ結果を社内に共有し、今後はインタビューによって顧客の本音を引き出していきたいと意欲的です。
ユーザー行動のログやCRM活動によるデータ分析でユーザーへの理解を深め、事業成長への効果を検証していきたいとしています。
※参考:株式会社LIFULL ー 導入事例 | 9segs
株式会社AbemaTVの活用事例
インターネットテレビサービス「ABEMA」を提供する株式会社AbemaTVは、N1分析®によって顧客の意見を把握し、「仮説を確かめられるようになった」「チームで共通認識を持てるようになった」とメリットを感じています。それまでは直感的な分析になりがちだったものの、N1分析®の導入によってデータの数値化・言語化が進み、肌感が正しかったのかどうかを判断しやすくなり、PDCAを回しやすくなったとしています。
過去のデータとの比較や、自社・他社サービスの顧客セグメントの変遷などを把握することにも役立つとしており、定期的な調査をしています。
※参考:株式会社AbemaTV ー 導入事例 | 9segs
ジンズホールディングス「JINS」の活用事例
アイウエアブランド「JINS」を展開するジンズホールディングスも、N1分析®を活用している企業の一つで、顧客の分布把握などに活用されました。ロイヤル顧客の数が想定より少ないことに気付けた一方で、ノンユーザー・ライトユーザーの割合が予想より多く、活路を見いだせたとのことです。
これにより購買頻度を高めることがロイヤル化の促進に役立つのではと分析できたとされています。
※参考:株式会社ジンズ ー 導入事例 | 9segs
まとめ
N1分析®を成功させるためには「対象者の選定」「インタビューの質」「得られたインサイトの解釈と汎用性の検討」が大切です。適切な手順でN1分析®をすると共に、導入企業の事例を参考にすると、今後のさらなる成長につなげられます。
あわせてN1分析®の注意点も意識し、効率良く顧客理解やマーケティング活動に利用していきましょう。





