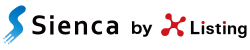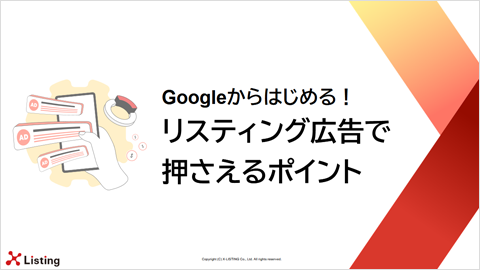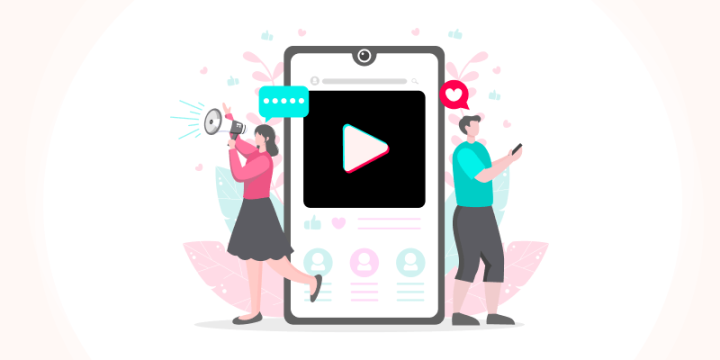Google広告とMeta広告を徹底比較|違いを知り、成果を伸ばす活用術
「Google広告とMeta広告、どちらを使うべきか迷っている…」
「両方やっているけれど、違いがいまいち理解できていない…」
このような悩みを持っている広告担当者の方も多いのではないでしょうか。
Google広告とMeta広告は、いずれも主要なデジタルマーケティング手法ですが、配信先・ターゲティングの仕組み・費用体系・適した目的などに明確な違いがあります。
この記事では、両者の特徴や使い分けのポイントをわかりやすく整理し、自社の課題やゴールに応じて成果を最大化するための活用術を解説します。
広告における「検索型・SNS型」の違いを理解し、あなたのビジネスに最適な広告戦略を見つけましょう。
株式会社クロスリスティングでは、Google広告やMeta広告を含めた広告運用コンサルティングを提供しております。BtoC、BtoB問わず、様々な業種業態での広告運用で得た知見に基づき、最適な広告プランニングをご提案します。
⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら
WEB広告媒体徹底比較ガイド!特徴、商材との相性、費用感を網羅的にまとめています。ダウンロードは無料です。
⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
Google広告とMeta広告、それぞれの特徴と概要
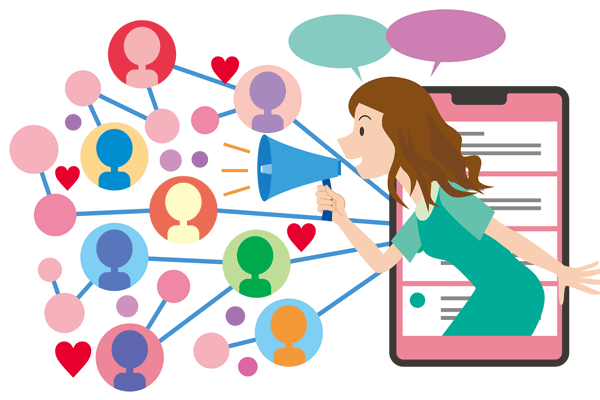
デジタル広告の世界でよく比較されるGoogle広告とMeta広告は、それぞれ異なる強みを持っています。
まずは、Google広告・Meta広告それぞれの概要や特徴について見ていきましょう。
Google広告(旧Google AdWords)とは?
Google広告(旧Google AdWords)は、世界最大の検索エンジンであるGoogleが提供する広告プラットフォームです。
主に、ユーザーが特定のキーワードで検索した際の検索結果ページに表示される検索広告(リスティング広告)と、Googleと提携するウェブサイト上に表示されるディスプレイ広告の2種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 検索広告(リスティング広告) | ユーザーが検索したキーワードに連動して、検索結果の上部や下部に表示されるテキスト広告。すでに情報収集や購入を検討している、意欲の高いユーザーにリーチしやすい点が特長。 |
| ディスプレイ広告 | Googleの提携サイトやアプリ上に、バナー形式で表示される画像や動画の広告。視覚的に訴求し、幅広いユーザー層にアプローチするのに適している。 |

検索広告の例

ディスプレイ広告の例
このように、Google広告はユーザーの検索意図に基づいたアプローチや、広範なリーチが可能な点が特徴です。
特に、購入意欲の高いユーザーへのアプローチや、高い検索ボリュームを持つ市場での活用に向いています。

Meta広告(Instagram・Facebook広告)とは?
Meta広告は、FacebookやInstagramといったMeta社が提供するSNSプラットフォームに広告を配信できるサービスです。

Facebook広告の例(画像出典:https://www.facebook.com/business/ads)
Meta広告では、ユーザーの年齢、性別、地域といったデモグラフィック情報に加え、興味関心や行動履歴に基づいた詳細なターゲティングが可能なため、潜在顧客へ効率的にアプローチできるのが特徴です。
また、ビジュアルを重視した広告フォーマットが豊富で、画像や動画を活用してユーザーの関心を引きつけやすいメリットもあります。
そのため、ブランド認知を高めたい場合や、まだ購買意欲が高くない潜在層にアプローチしたい場合に特に効果的です。

そもそもGoogle広告とSNS広告は何が違うのか?
Google広告とMeta広告を含むSNS広告の違いは、以下の通りです。
| 比較項目 | Google広告 | SNS広告(Meta広告含む) |
|---|---|---|
| アプローチ | ユーザーの検索意図(顕在層)にアプローチ | ユーザーの興味関心(潜在層)にアプローチ |
| 目的 | コンバージョン獲得、リード獲得 | 認知拡大、ブランドエンゲージメント |
| ターゲティング | キーワード、デモグラフィック、オーディエンスリスト | 詳細なデモグラフィック、興味関心、行動、カスタムオーディエンス |
Google広告とSNS広告の最大の違いは、ターゲットユーザーへのアプローチ方法です。
Google広告は、ユーザーが特定のキーワードを検索した際に表示されるため、「今まさにその情報や商品を探している」という顕在層にリーチできます。
一方、Meta広告を含むSNS広告は、ユーザーの年齢、性別、興味関心、行動履歴といった詳細なプロフィール情報に基づいて広告を配信します。つまり、まだ明確な購買意欲はないものの、潜在的な興味を持つユーザー(潜在層)にアプローチするのに適しています。ユーザーの「興味関心」に基づいたターゲティングと言えます。
このように、両者はユーザーの行動や心理フェーズの異なる層に効果的にアプローチできるため、一概に「どちらが良い」というものではありません。
広告運用によって高い成果を上げるには、それぞれの特性を理解し使い分けることが重要です。
Google広告とMeta広告の違いを比較分析
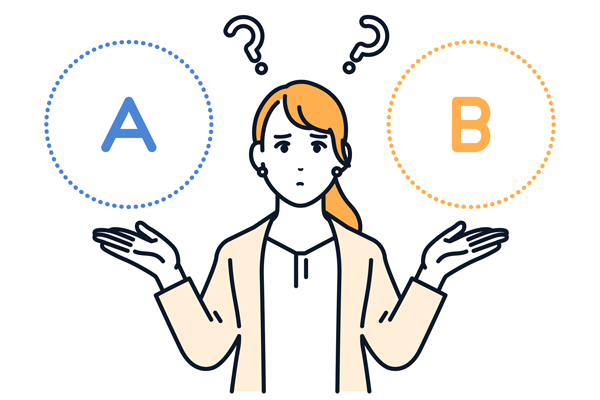
Google広告とMeta広告では、主に以下の4点で違いがあります。
- 配信プラットフォーム・ユーザー層の違い
- 「検索意図」と「興味関心」のターゲティングの違い
- 広告掲載面・フォーマットの違い
- 課金方式の違いと費用対効果の考え方
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
配信プラットフォーム・ユーザー層の違い
Google広告とMeta広告は、それぞれ異なるプラットフォームで配信され、リーチできるユーザー層にも違いがあります。
| 広告媒体 | 主な配信プラットフォーム | 主なユーザー層 |
|---|---|---|
| Google広告 | Google検索結果、Googleディスプレイネットワーク、YouTubeなど | 特定の情報を検索しているユーザー、すでに商品やサービスに関心が高いユーザー層 |
| Meta広告 | Facebook、Instagram、Messenger、Audience Network | ソーシャルメディアを利用する幅広い層(特にInstagramは若い層やビジュアル重視のユーザーに強い) |
Google広告は、ユーザーが「検索」という行動を起こした際にアプローチできるため、顕在層へのリーチに強みがあります。
一方、Meta広告は、ユーザーの年齢、性別、興味関心、行動履歴などに基づいた詳細なターゲティングが可能で、潜在層も含めた幅広いユーザー層にアプローチしやすい特徴があります。
特にFacebookやInstagramは、ビジュアルによる訴求が効果的で、ブランド認知向上にも適しています。
「検索意図」と「興味関心」のターゲティングの違い
Google広告とMeta広告では、ターゲティングのアプローチが大きく異なります。
Google広告:検索意図ターゲティング
- ユーザーが能動的に検索したキーワードに基づいて広告が表示されます。
- すでに商品やサービスに関心を持ち、具体的な情報収集や購買行動の段階にあるユーザーにリーチしやすいです。
- 例:「〇〇 購入」「〇〇 価格」「〇〇 使い方」など、明確なニーズを持つユーザーをターゲットにします。
Meta広告:興味関心ターゲティング
- ユーザーの年齢、性別、地域といったデモグラフィック情報に加え、興味関心や行動履歴に基づいて広告が表示されます。
- まだ特定のニーズが明確でない潜在顧客に対し、関心を引くクリエイティブでアプローチするのに適しています。
- 例:ファッションに興味がある、特定のスポーツが好き、最近旅行関連のページを見ている、といったユーザー属性をターゲットにします。
このように、Google広告は「欲しい」と思っている人に、Meta広告は「もしかしたら興味があるかも」という人にアプローチするのに強みがあります。
広告掲載面・フォーマットの違い
Google広告とMeta広告では、広告が表示される場所や形式にも大きな違いがあります。
| Google広告 | Meta広告 | |
|---|---|---|
| 掲載面 | Google検索結果ページ、Googleディスプレイネットワーク(提携Webサイトやアプリ)、YouTubeなど | Facebook、Instagram、Messenger、Audience Networkなど |
| フォーマット | ・検索広告(テキスト形式) ・ディスプレイ広告(バナー、レスポンシブ広告など) ・動画広告(YouTubeなど) | ・画像広告 ・動画広告 ・カルーセル広告(複数画像/動画) ・ストーリーズ広告 ・リール広告 |
このように、Google広告は検索意図に合わせたテキスト中心の広告に強く、Meta広告はユーザーの興味関心を引くビジュアル重視の広告に強みがあります。
課金方式の違いと費用対効果の考え方
Google広告とMeta広告は、それぞれ異なる課金方式を主に採用しており、費用対効果の考え方も変わってきます。
【Google広告の主な課金方式】
- CPC(クリック課金):広告がクリックされるたびに費用が発生します。「今すぐ客」へのアプローチに適しており、具体的な行動につながりやすいのが特徴です。
- CPM(インプレッション課金):広告が1,000回表示されるごとに費用が発生します。認知拡大やブランディング目的で利用されます。
- CPV(視聴課金):YouTube広告で、動画が一定時間視聴された場合に課金されます。
Google広告では、検索意図を持つユーザーにリーチするため、コンバージョン単価(CPA)や広告費用対効果(ROAS)を重視した運用が効果的です。
【Meta広告の主な課金方式】
- CPM(インプレッション課金):広告が表示されるだけで費用が発生します。Meta広告ではデフォルトで設定されることが多く、幅広い層への認知獲得に向いています。
- oCPM(最適化インプレッション課金):設定した目的に応じて最適化されながらインプレッション課金がされます。
- CPC(クリック課金):クリックごとの課金も可能ですが、MetaではCPMが一般的です。
Meta広告では、興味関心層にアプローチするため、リーチやインプレッション単価、あるいは目的としたアクション(コンバージョンなど)の単価を見て費用対効果を判断することが多いです。
どちらのプラットフォームも、自動入札機能などを活用することで、目的に応じた効率的な運用が可能です。
自社の目的に合わせて、最適な課金方式を選択し、費用対効果を最大化することが大切です。
広告効果を高めたい方必見、Facebook・Instagramの特徴と広告の勝ちパターンを徹底解説!ダウンロードは無料です。
⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
効果的なリスティング広告の設定手順と運用方法を解説したガイド。広告の掲載順位を向上させて、成果を最大化したい方におすすめ。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
Google広告のメリット・デメリット
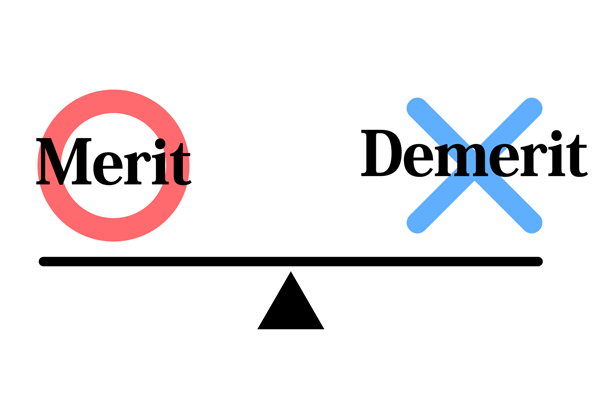
Google広告は、特定の目的を持ったユーザーにアプローチするのに非常に効果的な反面、いくつかの留意点も存在します。
メリット・デメリットを理解することで、より効果的な広告運用が可能になるでしょう。
ここからは、Google広告のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
Google広告を使うメリット
Google広告の最大の強みは、ユーザーの検索意図に基づいて広告を表示できる点です。
たとえば、「◯◯ 購入」「◯◯ 比較」など具体的なキーワードで検索しているユーザーは、すでに購買や申し込みを検討している段階にあることが多く、コンバージョンに直結しやすい傾向があります。
さらに、Googleは世界最大の検索エンジンであり、Google検索やYouTube、Gmail、数百万の提携サイトに広告を配信できるため、非常に広いリーチが可能です。
加えて、Googleディスプレイネットワーク(GDN)を活用すれば、まだ検索アクションには至っていない潜在層にも視覚的なアプローチができます。
バナー広告や動画を通じて、ユーザーの関心を高め、購買意欲を醸成する施策も展開可能です。
【Google広告のメリットまとめ】
- 検索キーワードに基づく配信で、購入意欲の高いユーザーにリーチできる
- Google検索やGmail、YouTubeなど幅広いメディアに広告を配信可能
- ディスプレイ広告で潜在層にも視覚的なアプローチができる
Google広告を使うデメリット
Google広告は非常に高機能な広告プラットフォームですが、すべてのビジネスやターゲット層に万能とは限りません。
特に、検索広告を中心としたキャンペーンでは、「今すぐ情報が欲しい・商品を探している」ユーザーへのアプローチに強い反面、潜在層への訴求には限界があります。
また、人気キーワードでは広告主間の競争が激しくなり、クリック単価(CPC)が高騰しやすい点にも注意が必要です。広告費の消化が早くなると、中小企業にとってはコスト面でのハードルとなるケースもあります。
さらに、検索広告ではテキスト中心のクリエイティブが基本なので、画像や動画などビジュアル要素で訴求したい商材には不向きな場面もあるでしょう。
【Google広告のデメリットまとめ】
- 人気キーワードではクリック単価が高騰しやすい
- 検索していない潜在層にはリーチしづらい
- ビジュアル訴求に不向きな場面がある(検索広告はテキスト主体)
Meta広告(Instagram・Facebook広告)のメリット・デメリット
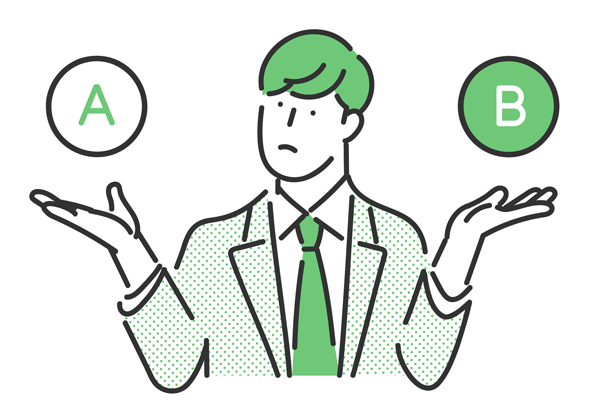
ここからは、Meta広告(Instagram・Facebook広告)を利用する際のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
Meta広告を使うメリット
Meta広告の最大のメリットは、ユーザーの興味関心に基づいた精密なターゲティングができる点です。
年齢、性別、地域だけでなく、詳細な興味関心や行動履歴に基づいたセグメント分けが可能です。
また、InstagramやFacebookは視覚的なコンテンツが中心のため、画像や動画を用いて商品やサービスの魅力を効果的に伝えることができます。
さらに、少額から広告運用を始めやすく、さまざまなクリエイティブやターゲティング設定をテストしやすい柔軟性も魅力です。
【Meta広告のメリットまとめ】
- 精密なユーザーターゲティングが可能
- 画像や動画で魅力を伝えやすい
- 少額からテスト運用しやすい
Meta広告を使うデメリット
Meta広告は、Google広告のように「今すぐ何かを探している」ユーザーではなく、SNSを閲覧している潜在層にアプローチすることが多いです。
そのため、広告を見たユーザーの購買意欲が必ずしも高いとは限らず、直接的な成果につながるまでに時間がかかる場合があります。
また、SNSユーザーは広告に対してネガティブな感情を持つこともあり、クリエイティブやターゲティングによっては敬遠されてしまうリスクもある点にも注意が必要です。
常に新しい情報やトレンドを意識し、ユーザーに寄り添った広告運用が求められます。
【Meta広告のデメリットまとめ】
- 購買意欲の低い潜在層へのアプローチが多い
- 直接的な成果につながりにくい場合がある
- ユーザーに敬遠されるリスクがある
具体的な広告フォーマットとクリエイティブのポイント
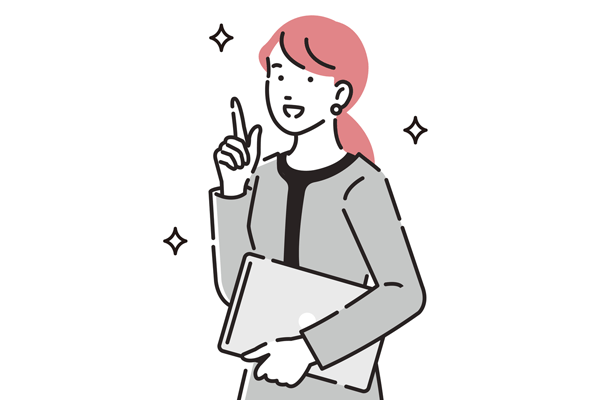
デジタル広告で成果を上げるためには、各プラットフォームの特性を理解し、そのフォーマットに最適化されたクリエイティブを作成することが不可欠です。
ここでは、主要な広告プラットフォームであるGoogle広告とMeta広告について、それぞれの主な広告タイプとクリエイティブ作成のポイントを具体的に解説します。
Google広告の主な広告タイプとクリエイティブ作成のポイント
Google広告は、検索エンジンからディスプレイネットワーク、YouTubeまで、幅広いユーザーにアプローチできる広告フォーマットを展開しています。
以下、各広告タイプのクリエイティブ作成のポイントをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
| 広告タイプ | クリエイティブ作成のポイント |
|---|---|
| 検索広告 | ・キーワードとの関連性を持たせた見出しと説明文を設定する ・「今なら20%OFF」など具体的な訴求文言を設定する ・LPとの一貫性(広告内容と遷移先の整合)を持たせる |
| ディスプレイ広告 | ・高品質なビジュアルを使用する ・レスポンシブ対応の素材を複数準備する ・明確なCTA(例:詳しくはこちらなど)を配置する |
| 動画広告(YouTube) | ・最初の5秒で興味喚起をする(スキップ対策) ・ストーリー性のある構成で共感を得る ・音声オフ対応(字幕や視覚表現を活用) |
| ショッピング広告 | ・白背景の高品質画像を使用する ・商品情報を正確に掲載し、最新性を保つ ・価格・セール表示で競合に勝つ工夫をする |
Meta広告の主な広告タイプとクリエイティブ作成のポイント
FacebookやInstagramを中心としたMeta広告は、精度の高いターゲティングと、ユーザーのフィードに自然に溶け込むフォーマットが特徴です。
以下、各広告タイプのクリエイティブ作成のポイントをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
| 広告タイプ | クリエイティブ作成のポイント |
|---|---|
| 画像広告 | ・モバイルファーストサイズ(1:1、4:5、9:16)で作成する ・画像内テキストは最小限にする(20%ルール意識) ・人物写真や図解などの視線を止めるデザインを採用する |
| 動画広告 | ・1〜3秒で惹きつけるために冒頭を工夫する ・テロップ・キャプションなどで無音再生対策をする ・UGC(ユーザー生成コンテンツ)風の自然なテイストを採用する |
| カルーセル広告 | ・ストーリーに一貫性を持たせる(例:課題→解決→商品) ・最後のカードでCTAを強調する ・パノラマ画像表現で注目を集める |
| コレクション広告 | ・魅力的なカバー素材で興味を引く ・テーマ性のある商品構成を採用する(例:夏アイテム特集) ・動的商品表示でパーソナライズする |
なお、これらのポイントに加え、A/Bテストを継続的に行い、どのクリエイティブがターゲットに響くのかを分析・改善していくことが大切です。
広告効果を高めたい方必見、Facebook・Instagramの特徴と広告の勝ちパターンを徹底解説!ダウンロードは無料です。
⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
効果的なリスティング広告の設定手順と運用方法を解説したガイド。広告の掲載順位を向上させて、成果を最大化したい方におすすめ。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら
パターン別で見るGoogle広告とMeta広告の使い分け

デジタル広告を効果的に活用するためには、広告の目的やターゲットユーザーに応じて、Google広告とMeta広告(旧Facebook広告)を適切に使い分けることが重要です。
ここでは、主要な目的別にどちらの広告が適しているのかを解説します。
「認知拡大」や「ブランディング」が目的の場合
「認知拡大」や「ブランディング」を目的とする場合、Meta広告の利用が向いています。
InstagramやFacebookといったプラットフォームは、画像や動画を中心としたビジュアルコンテンツに強みがあり、魅力的なクリエイティブを通じてユーザーの目を引き、印象に残りやすい広告を配信することが可能です。
また、膨大なユーザー基盤に加えて、年齢・性別・興味関心などの詳細なターゲティングができるため、狙いたい層に効率的に情報を届けることができます。
さらに、ユーザーの共感を得た広告は「いいね」やシェアといった行動を通じて自然に拡散され、ブランドや商品の認知度を広げる力を持っている点も、Meta広告がブランディングに向いている理由といえるでしょう。
「新規顧客獲得」や「サイト流入増加」が目的の場合
「新規顧客の獲得」や「サイト流入の増加」を目的とする場合は、Google広告とMeta広告の両方をうまく使い分けることが大切です。
Google広告のリスティング広告は、特定のキーワードを検索しているユーザー、つまりニーズが明確に顕在化している層に対して広告を表示できるため、コンバージョンにつながりやすいのが特徴です。特に、すでにサービスや商品を探している段階のユーザーにアプローチしたい場合には高い効果が期待できます。
一方、Meta広告はユーザーの興味関心や属性情報に基づいて配信されるため、自社の商品やサービスをまだ認知していない「潜在層」にリーチするのに適しています。
画像や動画といった視覚的なコンテンツを活用しながら、ユーザーの注意を引きつけ、サイト訪問のきっかけをつくることができるでしょう。
このように、どちらの広告もサイト流入を促進する力があるため、目的やターゲット層によって使い分けることで、より効果的な集客が可能になるでしょう。
「再購入促進」や「顧客エンゲージメント強化」が目的の場合
再購入促進や顧客エンゲージメント強化には、Meta広告が特に有効です。
Meta広告では、Facebookピクセルなどを使用して、ウェブサイト訪問者や過去に広告にエンゲージしたユーザーを特定し、リターゲティング広告を配信できます。
例えば、以下のような広告配信が可能です。
- ウェブサイト訪問者へのリターゲティング
- カートに商品を入れたまま離脱したユーザーに、その商品の広告を再度表示する。
- 特定の商品ページを閲覧したユーザーに、関連商品の広告を見せる。
- 既存顧客へのアプローチ
- 過去に購入した顧客に、新商品や関連商品を訴求する。
- 特定のアクション(例:アプリ利用、特定のコンテンツ閲覧)を行ったユーザーに、さらに深いエンゲージメントを促す広告を配信する。
このように、Meta広告のターゲティング機能を活用することで、一度接点を持ったユーザーに対して、パーソナライズされた広告を配信し、再購入やブランドへのエンゲージメントを高めることが可能です。
Google広告とMeta広告を組み合わせて活用する方法
Google広告とMeta広告は、それぞれ異なる強みを持っています。
そのため、どちらか一方だけでなく、両方を組み合わせて活用することで、より効果的な広告戦略を展開可能です。
ここからは、両媒体を併用する具体的な方法や、成功事例、予算配分の考え方について解説します。
顧客ファネルに応じた広告媒体の組み合わせ方の具体例
Google広告とMeta広告は、顧客が商品やサービスを認知し、最終的に購入に至るまでのプロセス(顧客ファネル)に合わせて使い分けることが有効です。
| ファネル段階 | 目的 | 主な活用媒体 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 認知(Awareness) | 知ってもらう | Meta広告 | 興味関心ターゲティングで幅広い層にリーチ、ビジュアルで商品イメージ訴求 |
| 興味・関心(Interest) | 興味を持つ | Meta広告 | より詳細な情報を含むクリエイティブでエンゲージメントを促進 |
| 比較・検討(Consideration) | 比較検討する | Google広告 | 検索連動型広告で特定のキーワード検索ユーザーに訴求、リスティング広告 |
| 行動(Action) | 購入・問い合わせ | Google広告 | コンバージョンに直結するキーワードで広告表示、ショッピング広告 |
上記のように、まずはMeta広告で潜在層にアプローチし、興味を持ったユーザーが検索行動に移った際にGoogle広告で訴求する、といった連携が考えられます。
Google広告とMeta広告の併用例(想定ケーススタディ)
ここでは、典型的なケーススタディとして、サービスの導入検討期間が長く、質の高い見込み顧客(リード)の獲得が課題となりやすいB2B向けSaaSビジネスを想定してみましょう。このようなケースでは、顧客の検討プロセス(ファネル)に応じて、Google広告とMeta広告の役割を明確に分けることで、効果的な広告戦略を構築できます。
まず、潜在顧客との最初の接点を作り、将来の顧客を育成(ナーチャリング)するために、Meta広告を活用します。具体的な施策として、Facebook上で「業務効率化のためのeBook」といった有益な資料を提供するリード獲得広告を配信。ここではターゲットを役職や業種で絞り込み、質の高い見込み顧客リストの獲得を目指します。さらに、eBookをダウンロードしたユーザーに対しては、後日、サービスの具体的な導入事例や活用法を紹介する動画広告を配信し、サービスへの理解を着実に深めてもらうというアプローチが有効です。
一方で、すでにツールの導入を具体的に検討している層を取りこぼさないよう、Google広告では検索広告を展開します。「プロジェクト管理ツール 比較」や「勤怠管理システム おすすめ」といった、購入意欲の高いキーワードで検索したユーザーに対し、サービスの無料トライアルや資料請求ページへ直接誘導する広告を表示させます。
この戦略の鍵となるのが、両プラットフォームの連携です。Meta広告で一度接点を持った見込み顧客が、後日Googleで関連キーワードを検索した際に、入札単価を通常より引き上げて広告を確実に表示させる設定を行うことが有効です。これにより、関心度が高まっているユーザーを競合サービスに奪われることなく、効果的に自社サイトへ誘導できます。
このような施策により、これまでアプローチが難しかった潜在層からのリード獲得数の増加が期待できます。さらに、両方の広告に接触したユーザーはサービスへの理解度が高まるため、最終的な商談に至る確率の向上も見込めます。
このように、Meta広告で需要を創出し、Google広告でその需要を刈り取るといった役割分担を明確にすることで、B2Bのような検討期間の長い商材においても、広告効果の最大化を目指せるのです。
両者を活用する際の予算配分の考え方
Google広告とMeta広告を併用する場合、予算配分は以下のように「広告の目的」と「ターゲットの検討段階」に応じて考えることが重要です。
- 認知拡大が主目的の場合:Meta広告に重点を置く
- 即効性のある獲得が主目的の場合:Google広告に重点を置く
- 両方のバランスを取りたい場合:顧客ファネルの各段階に合わせた比率で配分
例えば、ブランドや商品の認知拡大を主目的とするなら、視覚的な訴求力が高く潜在層にリーチしやすいMeta広告に予算を多めに配分するのが効果的です。
一方、購入や申し込みといった成果をすぐに求める場合は、顕在層へピンポイントでアプローチできるGoogle広告に重点を置くべきでしょう。
また、ファネル全体を意識した配分も有効です。上流(認知)にはMeta広告、中〜下流(比較・検討〜行動)にはGoogle広告を割り当てるなど、段階ごとの役割を明確にすると成果につながりやすくなります。
最初は少額からテスト運用を始め、CPAやROASといった指標をもとに、媒体ごとのパフォーマンスを見ながら柔軟に予算を調整していきましょう。
まとめ
本記事では、Google広告とMeta広告の違いについて詳しく解説しました。
Google広告は、検索意図に基づき「今すぐ買いたい」「比較検討している」ユーザーに訴求するのに適しており、高い購買意欲を持つ顕在層へのアプローチに向いています。
一方でMeta広告は、視覚的に訴求できる強みを活かし、ブランド認知の拡大や、まだニーズが明確でない潜在層へのアプローチに強みがあります。
そのため、「どちらを使うべきか」という二者択一ではなく、両方を連携させて活用するのが効果的です。
例えば、Google広告で獲得したユーザーに対し、Meta広告でリターゲティングをかけて再訪・購入を促すなど、ファネル全体を意識した広告戦略が成果につながります。
まずは、自社のビジネス目的とターゲット像を明確にし、それに合わせて広告媒体の役割を整理しましょう。
必要に応じて、広告運用の専門家に相談しながら最適な組み合わせを検討するのもおすすめです。