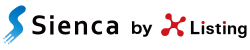データマネジメントとは?メリットと実施する際のポイント
現代のビジネスにおいて、データは単なる情報ではなく、企業の重要な資産として認識されています。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する中、このデータをいかに効果的に収集、整理、分析し、経営の意思決定に活かすか、そのための「データマネジメント」の考え方がますます重要になっています。
「データマネジメント」と聞くと、難しそう、どこから手をつければいいのか分からない、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、データマネジメントの基本的な概念から、そのメリット、そして実際に取り組む際の具体的なポイントまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
データマネジメントとは?CAO・CDO・DMOの役割

データマネジメントとは、データを「経営戦略を決定する上での重要な資産」と捉え、いつでも活用できる状態で継続的に維持・管理することを指します。これには、データの収集から保管、分析、活用はもちろん、データのライフサイクル全体を適切に統治する活動が含まれています。
データを常時利用可能な状態で保存しておくことで、データ収集にかかる時間を短縮し、社員誰もが同じデータを確認することが出来るため、共通認識を持った上で議論することが可能になります。データマネジメントが対象にする「データ」は幅広く、重要な決定を判断する際に活用できると考えられるなら、チラシの裏に書かれた雑多なメモもデータマネジメントの管理下に置かれることになります。
データマネジメント実施の際、社内で重要な役割を果たす役職として、「CAO」「CDO」「DMO」があります。それぞれ、これらの頭文字を取った略称です。
| 役職 | 主な責務 | 成果指標(例) |
|---|---|---|
| CAO(Chief Analytics Officer:最高分析責任者) | 分析基盤・アナリティクスの推進、データ活用プロジェクトのROI最大化 | 分析案件の成果、意思決定スピード、活用リードタイム |
| CDO(Chief Data Officer:最高データ責任者) | 全社データ戦略・ガバナンス策定、品質・セキュリティ管理、データ資産の最大限活用 | データ品質指標、法令遵守率、データ再利用率 |
| DMO(Data Management Officer / Office:データ管理者 / データマネジメント組織) | データ定義・整備・運用の実務、標準化・ツール導入、データマネジメントに関する責任を負う実行部隊の長 | データ定義数、メタデータ整備率、運用コスト削減率 |
※CAO、CDO、DMOは「データを活用して企業が抱える問題を解決する人」という意味合いで使われることが多いですが、組織によって役割の定義が異なる場合があります。DMOに関しては「Data Management Officer」ではなく「Data Management Office」として使われることが多く、この場合は、一人の人間の肩書きではなく、その組織に存在する「データマネジメント部署(組織)」の意味です。組織の規模や成熟度によっては兼務されることもありますが、まずは責任範囲を明確化し、意思決定の滞りを防ぐことが重要です。
データマネジメントのバイブル「DMBOK」とは

データマネジメントを体系的に理解する上で、国際的な指針となっているのが「DMBOK(Data Management Body of Knowledge)」です。これは、データマネジメントに関する知識を体系的にまとめた書籍であり、その定義はデータマネジメントの概念を理解する上で非常に役立ちます。DMBOKはデータマネジメントを家づくりにおける「設計」「基礎工事」「配管」「内装」といった各工程と捉え、それぞれの役割と関連性を整理しています。
データマネジメントを実施するメリット

データマネジメントを実施するメリットは3つ存在します。データマネジメントに取り組むことで、企業は様々な恩恵を受けることができます。
必要なときに必要なデータを利用できる
データマネジメントは、あらゆるデータを活用可能な状態で保存します。戦略を立案するときに必要なデータを保管場所からすぐに取り出せるため、意思決定の精度とスピードが向上します。また、データの保守・管理にあたって環境を設計する際に、データが有効なデータとして活用できる期限、保存に適した形式、データベースへのアクセス権の範囲、保守担当者などを決めるため、適切な管理の上でデータ保存がされます。また、データベース外にあるシステムの仕様書など(非構造化データ)は、メインデータとは別個に管理されるため、このような情報を参照しなければならないときにも困りません。
データ作成のための時間を削減できる
データマネジメントは、活用を前提としてデータを保存するため、データ加工などに要する時間を削減できます。データモデリング(データデザイン)によって、保存・管理しているデータ同士の関連性が明らかになっているため、関連データが欲しいときもスムーズなデータ検索が可能です。これにより、データ整備や再作成の工数が削減され、業務効率が向上します。
共通データを元にした判断ができ属人化を防げる
フォーマット化し、共通化されたデータを元に判断できるため、判断の属人化を防げます。データマネジメントを最適化することで、企業全体のデータライフサイクルが統一され、データの信頼性が向上します。これにより、意思決定が個人の経験や勘に頼ることなく、組織全体の再現性・透明性が高まります。
さらに、データマネジメントが最適化されると、部門間の連携がスムーズになり生産性が向上するなど、トータルコストを抑える結果にもつながります。
データマネジメント推進における課題
データマネジメントの最適化は多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかの困難も伴います。
初期投資コストや運用負荷の増加
土台作りには工数とコストがかかり、すぐに目に見える効果が出にくいと感じられることもあります。
部署間調整の難易度
全社的なデータ統合や活用は、複数の部門を横断するため、システムや慣習の違い、優先順位の違いから、調整に多大な労力がかかることがあります。
データサイロの再発リスク
組織内のシステムやデータがサイロ化(各部門で個別に管理され、連携されていない状態)していると、統合的なデータ活用が進まず、部分最適にとどまってしまう可能性があります。
セキュリティ・プライバシー問題
データを一元管理するからこそ、その保護はより重要になり、強固なセキュリティ対策が常に求められます。
データ品質評価の指標設定の難しさ
データの品質を客観的に評価し、改善していくための具体的な指標設定やその維持が難しい場合があります。
データマネジメント推進を担う人材の不在
全社的なデータを統合し、データマネジメントを最適化するためには、組織横断的に推進できるリーダーが不可欠です。
データマネジメント実施のポイント

企業がデータマネジメントを実施するときに意識しておくべきポイントを3つ紹介します。これらの困難を乗り越え、データマネジメントを成功させるためのポイントと成功要因を見ていきましょう。
データマネジメントに舵を切る目的を明確化する
データマネジメントの第一歩として最も大切なのは、「何のためにデータマネジメントを実施するのか」という明確な目的を設定することです。これが明確でないと、収集すべきデータや保管ルールなどの肝心な部分がぼやけてしまいます。
小さくはじめ徐々に大きくしていく
いきなり社内全てのデータを対象にするのではなく、データマネジメントの目的に沿った、必要最小限のデータから優先順位を決めて取り組みを始めることが成功への近道です。小さな成功体験を積み重ねることで、組織内の理解と協力が得られやすくなります。
上層部にデータマネジメントの理解者を増やす
データマネジメントの取り組みは一部署、一個人の取り組みだけでは限界があり、経営層の強力なリーダーシップが不可欠です。勉強会の開催や分かりやすい資料による説明など、根気強く取り組むことが大切です。また、トップダウンでデータマネジメントを実施することで、データの品質管理に必要な予算や法的な規制への対応もスムーズになります。
データマネジメント推進の3つの成功要因
データマネジメントを組織全体で成功させるためには、以下の3つの視点も重要です。
業務の問題解決から始める
現場で直面している具体的な業務課題を特定し、データマネジメントがその解決にどう寄与するかを示しましょう。
仕組みから変える
現場の負担を増やさずにデータ統一のメリットを享受してもらうため、データ管理の仕組み自体を組織・プロセス横断で統一することが重要です。データがどのように管理・利用されるかのプロセスを変えることで、利便性を提供できます。
ビジネスプロセス視点でビジョンを共有する
データマネジメントが組織全体にどのような恩恵をもたらし、各部門の役割や業務プロセスがどのように変わるのかを明確に示すことで、協力体制を築きましょう。
データマネジメントで実施する活動

データマネジメント実施にあたって行う必要がある活動は以下の通りです。
- 計画策定
まずは、データマネジメントを何の目的で実施するのか、成果地点はどこかなどの計画策定を行います。 - データ設計
次に行うデータ設計では、収集するデータについて「どのデータを」「どのような形式で」「どれくらいの期間」蓄積するのかなど、データに関する基本事項を定めます。 - データを保持するためのシステム構築
収集目的と収集データが決定したら、データを保持するためのシステムを構築します。 - データ利用と品質改善
データ収集が始まり活用できるようになったら、定期的にデータの品質を見直すといいでしょう。特にデータ収集・活用に利用しているツールは最新のものに変更すると利便性が上がることが多いです。
まとめ
データは、現代の企業経営において非常に重要な資産です。システム環境の混在、データの分散、組織のサイロ化、そしてデータ活用文化の未浸透といった課題につまずき、データマネジメントへの取り組みが進まない企業も少なくありません。
しかし、データマネジメントを最適化することは、データの信頼性を向上させ、意思決定の精度とスピードを高め、最終的には企業の競争力を大きく向上させることにつながります。
まずは、データマネジメントの目的を明確にすることから始め、データの収集、加工、蓄積、可視化、分析といったプロセスを一つずつ着実に進めていきましょう。そして、組織全体のデータリテラシーを向上させ、経営層を巻き込みながら、継続的にデータマネジメントを推進していくことが成功の鍵となります。
クロスリスティングでは、お客様のビジネス環境に応じた最適なデータ活用環境のご提案、CDP構築・運用の支援を行っています。自社データの活用で課題をお持ちでしたらぜひご相談ください。