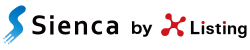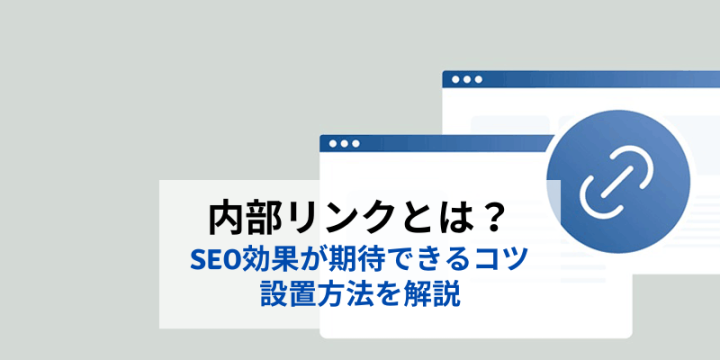GEO対策とは?SEOやLLMOとの違い、具体的な施策7つを徹底解説
近年、検索エンジンを取り巻く環境が急激に変化している中で、SEOに加えて注目を集めているのがGEO対策(Generative Engine Optimization)です。
これまでのSEOがGoogleの検索結果で上位表示を目指すものであったのに対し、GEOは生成AIが回答の中で自社情報を取り上げてくれるように対策する、という目的があります。
この記事では、GEO対策の基本的な概要からSEOやLLMOとの違い、具体的にやるべき7つの施策まで、初心者にもわかりやすく解説します。
「GEO対策って何?」「やらないとだめなの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
GEO(生成エンジン最適化)対策とは?
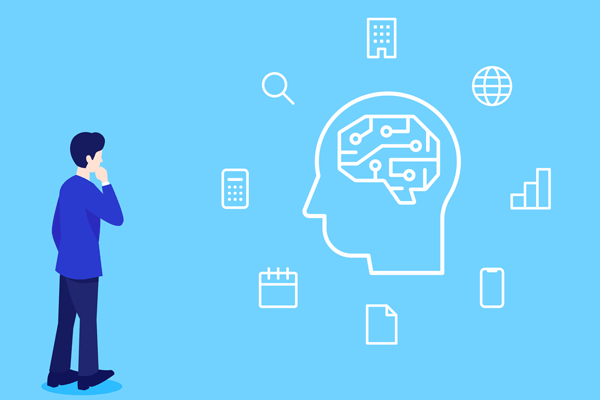
GEO(Generative Engine Optimization)とは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが検索エンジンとして使われる時代に向けた新しい最適化手法です。
従来のSEOがGoogleなどの検索結果で上位表示を目指すのに対し、GEOでは「AIの回答に自社の情報が取り上げられる」ことを目的とします。
たとえば、ChatGPTに「おすすめのWebコンサルティング会社は?」と質問したとき、自社名や自社サイトが具体的に挙がるようにするのがGEO対策の目的です。
今後、生成AIによる検索体験が主流になっていくことを考えると、GEO対策は「次世代の検索流入チャネル」を確保するための重要な取り組みといえるでしょう。
GEOとSEOの違いは?
GEOとSEOは、どちらも「検索に最適化する」という目的を持ちながら、そのアプローチや対象が異なります。
SEOはGoogleのような検索エンジンで上位表示されることを目指す施策ですが、GEOはChatGPTやGeminiなどの生成AIに「回答として自社情報を引用・言及されること」を目的としているからです。
実際の違いを以下の表で整理してみましょう。
| 項目 | SEO | GEO |
|---|---|---|
| 対象 | Google、Yahoo!などの検索エンジン | ChatGPT、Gemini、Perplexity、AI OverviewsなどのAI回答 |
| 表示形式 | 検索結果ページのリンク一覧 | 回答文内での引用や要約 |
| ユーザーの行動 | リンクをクリックして遷移 | 回答の中で完結、もしくは参照リンクをクリック |
| 最適化の要素 | キーワード、タグ設定、被リンク、E-E-A-Tなど | キーワード、タグ設定、文脈、E-E-A-T、引用性など |
表内の「最適化の要素」を見てもわかるとおり、GEOとSEOには共通している部分も多く、「GEO=SEOの進化系」ともいえます。
とはいえ、従来の検索エンジンに加えて、生成AIにも情報源として選ばれるようにするためには、SEOの基本を押さえつつGEO特有の視点を取り入れることが大切です。
LLMO・AIO・AEOとGEOの違いを比較
GEOと並んで注目されている用語に「LLMO」「AIO」「AEO」がありますが、それぞれの目的や対策内容は異なります。
名前は似ていても、取り組むべき領域は少しずつ異なるため、混同しないように整理しておきましょう。
| 用語 | 主な目的 | 対象 |
|---|---|---|
| GEO | 生成AIの回答に自社情報を表示させる | ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの検索AI |
| LLMO | LLMに正確な情報を学習・記憶させる | GPT-4やClaudeなどのLLMモデル本体 |
| AIO(AI Optimization) | 生成AIの回答に自社情報を表示させる | AI全般 |
| AEO | 検索エンジンの自動回答に情報を表示させる | AI Overviewsなどの自動応答型検索エンジン |
GEOはこれらの中でも「生成AIによる検索体験」に特化した概念です。
なお、これらの用語は業界内でも混同されており、たとえばAIOとGEOが同じ意味で使われるケースも少なくありません。
今後は業界内で使う用語も定まっていくことが予想されますが、現状は「違う意味として使われることもあるし、同じ意味の場合もある」と覚えておくとよいでしょう。


GEOが重要視されている3つの理由
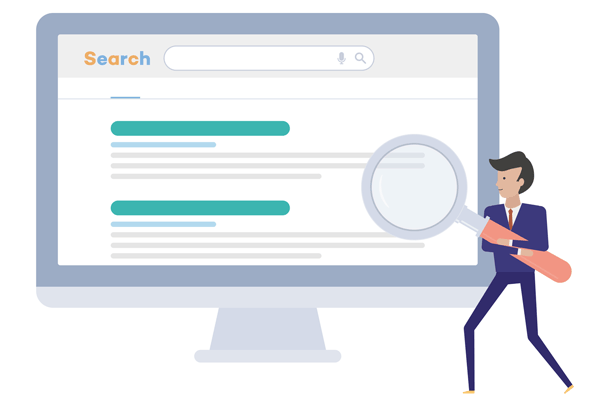
GEOが注目を集める背景には、検索体験そのものの大きな変化があります。
ここから、GEOが今後ますます重要になると考えられる3つの要因について詳しく見ていきましょう。
Googleの検索結果が変化しているから
GEOが注目される背景のひとつとして、Googleの検索結果の変化があります。特に話題になっているのが「AIO(AI Overviews)」の導入です。
AI Overviewsでは、従来のリンク一覧ではなく、検索結果の最上部にAIによる要約回答が表示されます。
つまり、ユーザーはリンクをクリックしてページを閲覧しなくても、検索結果ページ内で知りたい情報を得られてしまうのです。
この変化により、「ページリンクをクリックしてサイトを閲覧してもらうこと」が前提だったSEOだけでは十分に対応できなくなりつつあります。
AI Overviewsが普及した世界で自社をユーザーに知ってもらうためには、AIが参照する情報として選ばれることが重要になるため、GEOの視点が不可欠です。
たとえば、「GEO対策とは」と検索したときに、自社サイトが要約に取り上げられれば、大きな認知・信頼の獲得につながるでしょう。

ユーザー行動が変化しているから
GEO対策が求められるもう一つの理由は、ユーザーの検索行動そのものが変わってきていることです。
これまで多くの人はGoogleなどでキーワードを入力し、検索結果から必要な情報を自分で探していました。
しかし近年では、検索したあとにAIによる回答だけを見て検索行動が完結する「ゼロクリック検索」が増えています。
ゼロクリック検索が増えているということは、これまでSEOで自社サイトに流入していたユーザーを取りこぼしてしまうということです。
そんな中で「AIの答えに自社が含まれる」ことはユーザーとの新たな接点になります。
仮に直接的な流入にはつながらなかったとしても、「AIに聞くと、いつもあの会社の名前が出てくるな」という印象を持ってもらえれば、結果的に売上やコンバージョンなどにもつながる可能性があるでしょう。
新たな流入チャネルとしての価値があるから
GEO対策が重要視されるもう一つの理由は、SEOで培った資産を活かしながら、新たな流入チャネルを築ける点にあります。
従来のSEOでは、Google検索経由での流入を最大化することが目的でした。
しかし今後、ユーザーが生成AIを通じて情報を取得する機会が増える中では「AIに参照元・引用元として取り上げられるか」がアクセスの新たな鍵になります。
つまり、SEOで構築してきた高品質なコンテンツをベースにGEO対応を施せば、検索エンジンだけでなく、AI経由でもユーザーとの接点が増えるのです。
また、AIの回答に引用されることで、自然な形で認知や信頼性を獲得することにもつながります。
GEO対策に取り組むメリット
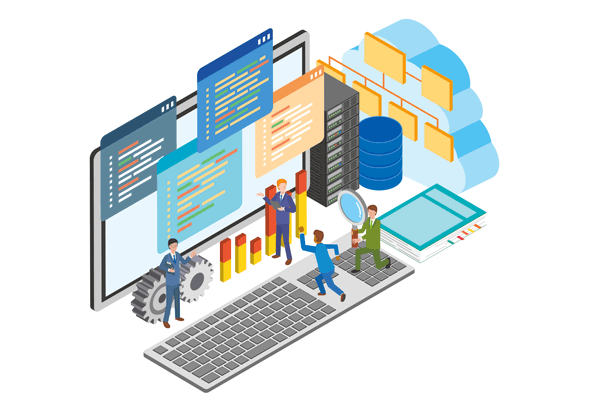
ここからは、GEO対策に取り組むことで得られる具体的な3つのメリットについて、解説します。
流入数の下落に対応できる
近年、SEOだけに依存した集客は限界を迎えつつあります。
実際AI Overviewsの導入以降、ゼロクリック検索が増えたことで、検索上位に表示されていても流入が減るといった事例は少なくありません。
このような変化に対して、GEOは有効な打ち手となります。
たとえば、ChatGPTに「おすすめの○○サービスは?」と聞いたとき、自社の名前がAIの回答文中に出てくれば、検索経由での流入が減ったとしても、別のルートで接点を持てるのです。
認知拡大や信頼性の獲得につながる
GEO対策に取り組むことで、生成AIによる「第三者評価」の形で自社が紹介される機会が増えるメリットもあります。
たとえば、ChatGPTに「信頼できる○○会社を教えて」と尋ねたとき、AIが自社サイトを引用して「○○会社は実績が豊富です」と回答すれば、それは“AIが選んだ中立的な評価”として受け止められるでしょう。
このように、GEOを通じてAIに自社情報が引用・要約されることで、ユーザーの信頼を自然に得られるのも大きな魅力です。
SEOとの相乗効果が期待できる
GEO対策はSEOの延長線上にあるため、両方を並行して取り組むことで相乗効果が期待できます。
生成AIは、権威性や信頼性の高いWebページを情報源として選ぶ傾向があり、その多くはGoogle検索でも上位に表示されているサイトです。
つまり、SEOで上位を獲得しているページは、GEOでも引用されやすくなります。
逆に、GEOを意識してE-E-A-Tや構造化データを整備すれば、その改善がSEOの評価にもつながるでしょう。
このように、SEOとGEOは相互補完の関係にあり、片方の施策がもう片方の成果を後押しするのです。
今すぐできるGEO対策のポイント7つ
GEOは新しい概念とはいえ、特別なツールやAIの知識が必要になるわけではありません。
これまでSEOで意識してきた施策をベースに、生成AIに最適化するポイントを押さえることで、十分に対応が可能です。
ここからは、SEO初心者でもすぐに取り組めるGEO対策の具体的な施策を7つ紹介します。
わかりやすい見出し構造を作成する
GEO対策では、生成AIが記事の構成を正確に読み取れるように、見出し構造を論理的かつ整理された形で設計することが重要です。
たとえば「h2:GEOとは?」「h3:GEOとSEOの違いは?」というように、階層構造を明確にしながらコンテンツの流れを作ることで、AIにも読みやすく、人にもわかりやすい記事になります。
過度に見出しが多すぎたり、順番が飛んでいたりすると、AIが記事の主旨を誤って解釈する原因にもなるので注意しましょう。
見出しに対する明確な答えを端的に記載する
生成AIは、「質問に対する答えがどこにあるか」を重視して情報を抽出しています。
そのため、GEO対策においては見出しで提示した問いに対して、すぐ下の段落で端的に答えを示すことが大切です。
たとえば「GEO対策とは?」という見出しの直後には、「GEO対策とは、生成AIに情報を引用・要約されることを目的とした最適化手法です」といったように、結論ファーストで明快な一文を置くことが望ましいでしょう。
E-E-A-Tを向上させる
GEO対策では、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の向上も欠かせません。
生成AIはWeb上の情報をもとに回答を生成する際、「どのサイトが信頼できる情報源か」を判断しています。
たとえば、以下のような要素を意識することで、AIに信頼性の高いサイトと認識されやすくなるでしょう。
- 著者情報の明示:著者の実績や専門領域を記載する
- 一次情報の掲載:自社のデータ、調査、インタビュー結果などを活用する
- 監修者の記載:第三者による監修表示を入れる
- 信頼できる出典の引用:政府機関・専門メディアなどから情報を引用する
これらの対策は、Googleの評価指標としても使われているため、SEOとGEOの両面で効果的です。
画像や動画などを活用する
GEO対策においては、画像や動画などの活用も有効です。
生成AIはテキストだけでなく、Webページ全体の構成やマルチメディア要素を読み取り、回答に活かすケースが増えています。
たとえば、以下のような要素はGEOにおいてプラスに働く可能性があります。
- 図解やフローチャート:複雑な情報をわかりやすく伝える
- 画像にalt属性を適切に設定:AIが内容を正確に理解するためのサポート
視覚的な要素はユーザーにとっても理解しやすく、AIにとっても“引用すべき情報”と判断されやすくなるメリットがあります。
検索だけでなくAIによる要約・紹介にもつながりやすくなるため、積極的に活用していきましょう。
構造化データを設定する
構造化データとは、検索エンジンや生成AIに対して「この情報は何を意味するのか」を明確に伝えるためのマークアップタグです。
GEO対策では、ページ内の情報をAIに正しく認識させるために、構造化データの設定が非常に重要です。
具体的には、以下のような構造化データが活用されています。
| タイプ | 用途例 |
|---|---|
| Article | 記事タイトル・著者・投稿日などの明示 |
| FAQ | よくある質問とその回答 |
| Product | 商品名・価格・レビュー情報などの提示 |
| Person / Organization | 著者や企業情報の明示 |
| VideoObject | 埋め込み動画の情報を伝える |
外部評価・サイテーションを獲得する
GEO対策においては、自社サイトや情報が他の信頼できるサイト・メディアで取り上げられているか(サイテーション)も重要な評価軸です。
信頼性の高い外部メディアやニュースサイトで繰り返し言及されている情報は、生成AIから「権威ある情報」と判断されやすく、回答に採用されやすくなるのです。
たとえば以下のようなサイテーション獲得施策が有効です。
- プレスリリース配信でニュースメディアに掲載される
- 業界団体や比較サイトに掲載される
- ブログやSNSで自社名・サービス名が言及される
- 専門家やインフルエンサーからの紹介・引用
外部メディアとの接点を意識的に増やしていくことが、AIに拾われる確率を高めるポイントです。
傾向を分析する
GEO対策を行ううえで欠かせないのが、生成AIにどのような情報が取り上げられているかを分析することです。
対策を講じても、どのようにAIに取り上げられているか、競合と比較してどの程度露出しているかがわからなければ、改善の方向性も見えません。
最近では、Ahrefsなど一部のSEOツールにおいて、生成AIでの露出傾向を可視化する機能が搭載され始めているので、積極的に活用しましょう。
GEOは一度対策して終わりではなく、継続的な検証と調整が求められる領域です。可視化ツールや生成AIでの実際の出力をこまめにチェックしながら、施策の精度を高めていきましょう。
GEO対策を行う際の注意点

GEO対策は、生成AIに選ばれるための工夫として注目を集めていますが、むやみに対策を進めてしまうと、かえってSEOやサイト全体に悪影響を及ぼす可能性もあります。
ここでは、GEO対策を進めるうえで見落とされがちな注意点や、今後のリスクを避けるために知っておきたいポイントを紹介します。
GEOの土台はSEOであることを理解する
GEO対策を行ううえで認識しておきたいのは、GEOはSEOの土台の上に成り立っているという点です。
生成AIは、Web上の情報をもとに回答を作成しますが、その多くはGoogleなどで評価されている“信頼性の高いページ”を優先的に参照しています。
つまり、SEOがしっかり施されたページでなければ、そもそもAIに発見・引用される可能性が低くなるということです。
たとえば、インデックスされていないページや、検索上位に表示されないページは、生成AIのクローラーにも見つかりにくくなります。
また、E-E-A-Tが弱いコンテンツや、構造が不明瞭なページは、AIにとって“引用しにくい”存在となるでしょう。
そのため、GEOだけに偏った施策をするのではなく、まずはSEOの基本を整えることが大切です。
「AIのための対策」は将来的にリスクがある
GEO対策に取り組むうえで注意したいのが、「AIに好かれるためだけの対策」を過剰に行うことです。
これは、かつてのブラックハットSEOが一時的に効果を発揮したものの、Googleのアルゴリズム進化によって淘汰された流れと非常によく似ています。
たとえば、以下のような行為は、短期的に効果を期待できる一方で、ユーザー体験を損ねたり、将来的に信頼性を失うリスクも伴います。
- 構造化データを不自然に多用する
- 実在しない専門家を“監修者”として記載する
- AIに引用されることだけを目的としたQ&A量産
AIも進化を続けており、今後は「より人間らしい読みやすさ」や「真の専門性」が求められるようになるはずです。
目先の流入や効果ではなく、本質的な情報価値や信頼性をベースにした対策を行うことを心がけましょう。
まとめ
本記事では、GEO対策について基本的な考え方や具体的な施策まで詳しく解説しました。
生成AIが検索の入り口として広がりつつある現在、GEO対策は、これからの集客や認知獲得において欠かせない取り組みとなりつつあります。
とはいえ、GEOはSEOの上に成り立っているという前提を忘れてはいけません。AIだけでなく、ユーザーにも価値あるコンテンツを届けることが、長期的な成果につながるということを覚えておきましょう。
生成AI時代の波に乗り遅れないためにも、本記事で紹介した施策を参考に今のうちからGEO対策に取り組んでみてください。