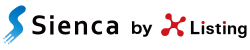LLMOとは?SEOやAIOとの違いや具体的な対策方法をわかりやすく解説
「LLMOって何?SEOとは違うの?」
「具体的に何をやればいいの?」
このような疑問を抱えながらLLMOについて調べている方は多いのではないでしょうか。
LLMO(Large Language Model Optimization)は、ChatGPTなどの生成AIに正しく自社情報を認識・引用してもらうための新しい最適化手法です。
SEOやAIOと似た言葉ではありますが、それぞれ目的や対策対象が異なります。
本記事では、LLMOの基本的な意味や他の最適化手法との違い、なぜ今注目されているのか、そして具体的な施策までをわかりやすく解説します。
「生成AI時代のSEO対策」を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
LLMOとは?
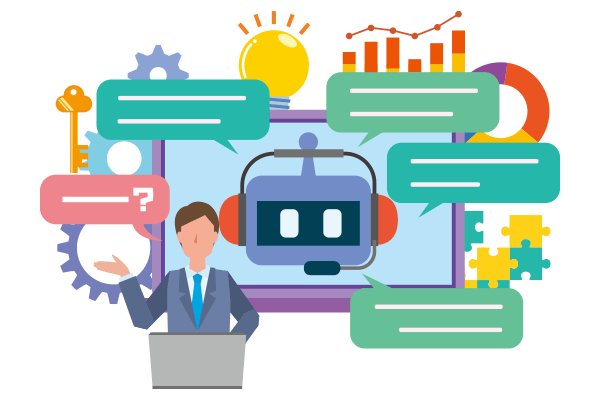
LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGeminiなどの大規模言語モデル(LLM)に自社情報を正しく学習・認識させるための手法です。
従来のSEOが「Googleに評価されて検索上位に表示される」ことを目指すのに対し、LLMOは「生成AIに参照・引用されること」を目的とします。
たとえば、ChatGPTに「おすすめの会計ソフトは?」と質問したとき、自社名や製品が自然に回答に含まれていれば、LLMOがうまく機能している状態です。
最近では、SEOに加えてAIOやGEOなどの新しい概念も登場していますが、中でもLLMOは、生成AI時代の土台となる対策として注目を集めています。
今後、検索行動がAI中心にシフトしていく中で、LLMOへの対応が新たな集客チャネルを開く鍵になるでしょう。
そもそもLLMとは?
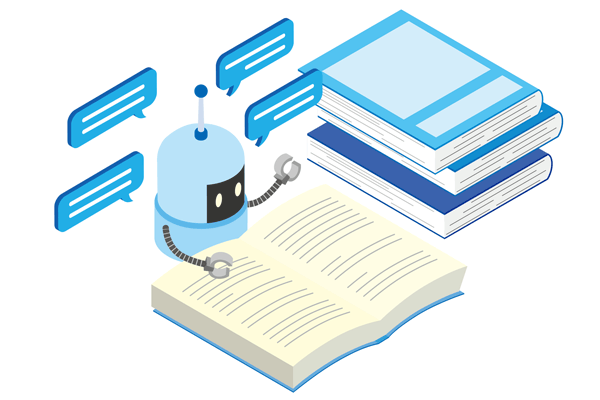
LLMとは、膨大なテキストデータをもとに学習し、人間のような自然な文章を生成できるAIのことです。
検索やチャット、文章生成など、さまざまな用途で活用されており、現在の生成AIブームの中核を担う存在といえます。
代表的なLLMは、以下のとおりです。
- ChatGPT(OpenAI)
- Gemini(Google)
- Claude(Anthropic)
これらのLLMは、Web上の情報、論文、会話データなどを学習しており、質問に対する回答や要約、文章作成まで対応可能です。
LLMOでは、このLLMがどのように情報を「記憶」し、どんな基準で「引用」するかを理解したうえで、自社情報を正しく届ける工夫を行うことがポイントになります。
LLMOとSEOの違い
LLMOとSEOは、どちらも「情報を適切に届けるための最適化手法」ですが、最適化の対象・目的・評価基準が異なります。
SEOはGoogleなどの検索エンジンで上位表示されることが目的であるのに対し、LLMOはChatGPTなどの生成AIに参照されることがゴールです。
そのほか、両者には以下のような違いがあります。
| 項目 | SEO | LLMO |
|---|---|---|
| 対象 | Google、Yahoo!などの検索エンジン | ChatGPT、Gemini、Claudeなどの生成AIや、AI Overviewsなどの自動回答型検索エンジン |
| 表示形式 | 検索結果の一覧ページ | 回答文内への引用・要約 |
| ユーザー体験 | ページリンクをクリックして遷移し、必要な情報を得る | AIからの回答によって直接情報を得る |
| 評価軸 | 検索順位・CTR・被リンクなど | 引用数・参照数・自然言及の有無など |
ただし、LLMOとSEOは対立するものではなく、相互に補完しあう関係です。
SEOで上位表示されたページは、LLMにとっても「信頼できる情報源」として認識されやすく、LLMOの成功にもつながります。
「LLMOが登場したからSEOは不要」というわけではなく、今後はSEOで築いた資産の上にLLMOを重ねていく姿勢が求められるでしょう。
LLMOとAIOの違い
LLMOとAIO(AI Optimization)は、どちらも生成AIに向けた最適化手法ですが、最適化の目的とアプローチが異なります。
混同しやすい言葉ですが、対策の軸を理解しておくことで、より的確に使い分けられるようになります。
| 項目 | LLMO | AIO(AI最適化) |
|---|---|---|
| 対象 | ChatGPT、Claude、GeminiなどのLLM本体 | AI全般(LLM含む、検索AI、レコメンドAIなど) |
| 目的 | AIに“記憶”させ、回答文で自社情報を引用させる | AIに正しく“理解”させ、処理しやすくする |
| 主な施策 | サイテーション獲得、E-E-A-T強化、情報の一貫性、わかりやすい見出し構造・内容など | シンプルな表現、明確な文脈、メタ情報の最適化など |
| 位置づけ | 信頼性のある情報源として採用されるための対策 | 読み取りやすい構造で処理されやすくする工夫 |
なお、業界内においては「LLMO=AIO」として扱われるケースも少なくありません。
新しいマーケティング用語だからこそ定義が定まっておらず、両者の違いや比較されるポイントもさまざまです。
そのため、現時点ではLLMOとAIOを厳密に使い分ける必要性はあまりないでしょう。
LLMOが今注目されている理由
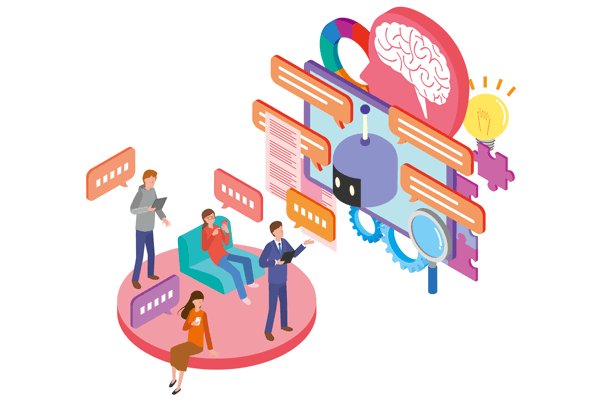
LLMOが注目されている背景には、検索エンジンの役割が大きく変わりつつあることがあります。
近年では、ChatGPTやGeminiといった生成AIが「調べるツール」として使われ始め、Google検索に頼らないユーザーが増えています。
この流れを象徴するのが「ゼロクリック検索」と呼ばれる現象です。
従来は「検索 → 検索結果からページリンクをクリック → 情報取得」という流れが一般的でしたが、今はAIが提示する回答だけで満足してしまうユーザーが増えています。
つまり、いくらSEOで上位表示されていても、AIに引用されなければユーザーとの接点が失われる時代になってきているのです。
こうした中で、SEOだけではカバーしきれない新しい検索行動に対応するために、今LLMOに取り組む企業が増えているのです。
今すぐできるLLMO対策9選
「LLMOが重要なのはわかったけれど、具体的に何をすればいいの?」という方も多いでしょう。
そこでここからは、今すぐ始められる実践的なLLMO対策を紹介します。
SEOで検索上位を目指す
LLMOはSEOとは異なる概念ですが、検索上位に表示されているページは、生成AIにも“信頼性が高い情報源”として認識されやすい傾向があります。
そのため、まずは従来どおり、Google検索で上位を目指すことが大切です。
SEOで検索上位を取るためには、以下の基本を押さえておく必要があります。
- キーワードに対する明確な回答を記載する
- 読者のニーズに沿った構成と導線設計
- 内部リンクやページスピードなどのテクニカルSEO対策
- 被リンクやサイテーションなどの外部SEO対策
- 定期的なコンテンツ更新と品質管理
SEOとLLMOは切り離せるものではなく、検索上位を狙うことがそのままAIへの露出強化にもつながるという視点で考えることが大切です。
わかりやすい見出し構造を作成する
生成AIは、Webページの構造をもとに情報を整理・理解しています。
特に見出し(hタグ)の使い方は、AIにとってその情報が「何について書かれているか」を判断する大きな手がかりになります。
LLMOにおいてもSEOと同様に、以下のような論理的で階層的な見出し設計を心がけましょう。
| 適切な見出し構造の例 |
|---|
| h2:LLMOとは? └ h3:LLMOとSEOの違い └ h4:表示形式の違い └ h4:評価基準の違い h2:LLMOのメリット └ h3:メリット① └ h3:メリット② h2:LLMOのデメリット └ h3:デメリット① └ h3:デメリット② |
h2はトピック単位、h3は具体的な項目ごとというルールを守ることで、AIにも人間にもわかりやすいページになります。
また、見出しにキーワードを含めることで、AIが「何についての情報か」を明確に理解しやすくなり、引用や要約の精度向上にもつながります。
LLMOを意識するなら、まずはAIが読み取りやすい構造をつくることが第一歩です。
引用しやすい文章を作成する
LLMOでは、生成AIが引用しやすい文章を書くことも重要なポイントです。
AIは人間と同じように文脈を理解しているように見えますが、実際には「明確な定義」「簡潔な回答」「整った文構造」を優先的に引用する傾向があります。
そのため、以下のような文章を意識すると、引用されやすくなる可能性があります。
- 結論ファーストで書く
- 一文を短く、主語と述語を明確にする
- 1段落に1テーマを意識し、内容を区切る
- 必要に応じてリストや表形式を活用する
たとえば「LLMOとは?」という見出しの直後に「LLMOとは、大規模言語モデルに自社情報を認識・引用させるための最適化手法です」と書かれていれば、AIにとってはそのまま回答に転用しやすい形式といえるでしょう。
上位サイトで自社について言及してもらう
LLMOにおいては、自社サイトだけでなく、外部の信頼性の高いサイトから“言及されているか”が非常に重要です。
特に効果があるのは、Google検索で上位表示されているサイトや、ドメイン評価の高いメディアからの言及です。
たとえ自社サイトへのリンクが付いていなくても、「社名」「サービス名」「代表者名」などのテキストが上位記事で繰り返し登場することで、AIの学習モデルに組み込まれやすくなります。
LLMO対策では「自分のサイトを整えるだけでなく、誰にどこで言及してもらうか」も重要な視点です。上位サイトとの接点を意識し、引用される機会を増やしていきましょう。
質の高いコンテンツを作成する
LLMO対策では、AIに正しく引用・学習されるためにも、質の高いコンテンツの継続的な発信が不可欠です。
中でも重要なのが、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の要素を満たしたコンテンツの作成です。
生成AIは、ただ情報が多いだけでなく、誰がどの立場から語っているかやその情報に裏付けがあるかを評価しています。
具体的には、以下のようなポイントを押さえたページ作成を心がけましょう。
- 一次情報の活用
- 専門家の監修・著者情報の明示
- 信頼できる外部ソースの引用
- 古い情報の定期更新
- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用
コンテンツの信頼性と情報の鮮度は、SEOと同様にLLMOでも重視される評価軸です。
サイトの表示スピードを改善する
LLMO対策においては、ユーザー体験の快適さも間接的に生成AIへの評価に影響します。
特に「ページの表示スピード」は、SEOだけでなく、AIが情報を読み取り・処理するうえでも重要な要素のひとつです。
そのため、極端にページの表示速度が遅い場合は、以下のようなポイントで対策するとよいでしょう。
- 画像サイズを最適化する(WebP形式などを活用)
- 不要なJavaScriptやCSSの読み込みを減らす
- サーバーの応答速度を改善する(高性能サーバーの導入など)
- 遅延読み込み(Lazy Load)の導入
表示速度が遅いページは、AIクローラーが離脱しやすく、全文を正しく取得できない可能性があるので注意してください。
サイト構造を最適化する
生成AIは、Webページをただ読むだけでなく、「どの情報がどこにあるか」「何を意味しているか」といった構造まで理解しようとします。
そこで重要になるのが、サイト構造です。
特にJavaScript主体で構成されたページや、非論理的なHTML構成は、AIにとっても“認識しづらいページ”になってしまうリスクがあります。
そのため、以下のようなポイントでサイト構造を見直してみましょう。
- HTMLはセマンティックタグで記述されているか
- JavaScriptに依存していないか
AIに正確に読み取ってもらうには、構造が整っていることが前提です。「人にもAIにもやさしい設計=LLMO対策の基本」として、今一度サイト全体の構造を見直してみてください。
構造化データを設定する
構造化データとは、Webページ内の情報を検索エンジンやAIが「機械的に理解しやすい形式」に変換して伝えるマークアップのことです。
LLMOでは、生成AIに自社情報を正しく認識・引用してもらうために、以下のような構造化データの活用が重要とされています。
| 構造化データの種類 | 用途例 |
|---|---|
| Article | 著者名・投稿日・記事タイプの定義 |
| Organization | 会社名・所在地・ロゴ・SNS情報の明示 |
| FAQPage | 質問と回答を構造的に伝える |
| Product | 商品名・価格・レビュー・在庫状況の定義 |
| Person | 著者や監修者の情報を明示 |
構造化データはSEOとLLMOの橋渡し的な役割を果たすため、導入を強くおすすめします。
サイテーションやブランディングに取り組む
LLMOでは、自社名やサービス名がWeb上でどれだけ言及されているかが非常に重要です。
これを「サイテーション」と呼び、仮に自社サイトへ向けたリンクが付いていなくても、文章内での言及が多いほどAIにとっての信頼性が高まります。
特に、ドメイン評価が高いサイトやメディアからの言及は、生成AIにとって重要な判断材料となります。
なお、サイテーション評価を高めるには、以下のような施策が有効です。
- プレスリリースを継続的に配信し、メディア露出を増やす
- 業界ポータルサイトや専門メディアへの掲載依頼
- 比較サイト・レビューサイトでの掲載機会を増やす
- サービスロゴやブランド名の統一、公式情報の整備
こうした露出が積み重なることで、生成AIの回答内に自然と自社情報が取り上げられるようになるでしょう。
LLMO対策チェックリスト
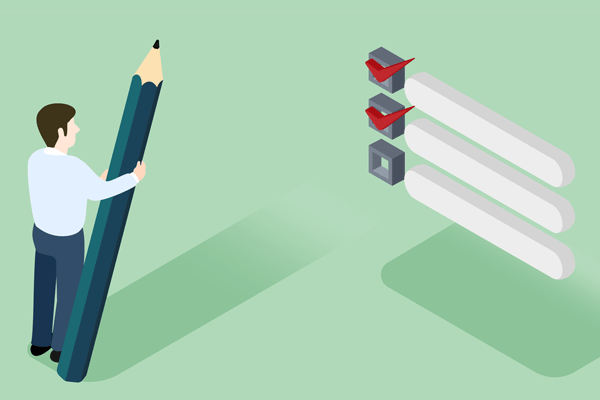
ここでは、これまで紹介した「今すぐできるLLMO対策9選」をチェックリスト形式で一覧化しました。自社のサイトや運用状況と照らし合わせながら、実施状況を確認してみましょう。
| 対策内容 | 完了チェック |
|---|---|
| 対策キーワード用の記事でSEOで検索上位を獲得できている | □ |
| 見出し構造を論理的に設計している | □ |
| 結論ファーストで引用しやすい文章を書いている | □ |
| 上位サイトからの言及を得ている | □ |
| E-E-A-Tを意識した高品質なコンテンツを作成している | □ |
| ページの表示スピードを最適化している | □ |
| サイト構造をHTMLベースで最適化している | □ |
| Schema.orgで構造化データを設定している | □ |
| サイテーションやブランディング施策を実施している | □ |
すべての項目を一度に実施する必要はありません。まずは「実施中」の項目を一つでも増やすことが、生成AI時代の情報露出力アップへの第一歩になります。
LLMOの効果測定の方法

ここでは、LLMO対策の成果を測るうえで活用できる代表的な指標を紹介します。KPI設計で悩んでいる方は参考にしてみてください。
AIOでの引用数
LLMOの効果測定でもっとも確認しやすいのが、生成AIによる自社情報の引用状況です。
たとえば、ChatGPTやGemini、Perplexityに特定の質問を投げたとき、自社名やコンテンツが引用・言及されているかどうかがひとつの目安になります。
具体的には、以下のような方法で引用状況を確認することが可能です。
- ChatGPTやGeminiに想定質問を投げ、自社が回答内に登場するか確認
- PerplexityなどのAI検索で、自社サイトが引用元としてリンクされているかを確認
- SEOツールの一部機能でAI引用数を確認
自社サイトの内容が引用されていれば、それはLLMO対策がうまくいっている証拠です。逆に出てこない場合は、情報の構造や信頼性の見直しが必要かもしれません。
AI経由での流入数
LLMO対策の成果を定量的に測る方法として、GoogleAnalyticsでの流入分析も有効です。
現在のGA4では、ChatGPTやPerplexityなどの生成AI経由のトラフィックが「参照元(Referrer)」として表示されており、AI経由でどれだけ自社サイトにアクセスがあったかを把握できます。
ChatGPT経由のアクセスは「chatgpt.com」や「chat.openai.com」、Perplexityは「perplexity.ai」 などとして表示されるため、流入元にこれらが表示されていないか確認してみましょう。
指名検索数
LLMOの効果を測定するうえでは、指名検索数も有効な指標のひとつです。
指名検索とは、ユーザーが「社名」「ブランド名」「商品名」などを含むキーワードで検索する行動のこと。
指名検索が増えている場合、次のような可能性が考えられます。
- 生成AIの回答に自社名が登場し、ユーザーの興味を引いた
- 外部メディアやSNS、UGCなどの言及が増え、認知が広がった
- サイテーション効果やブランディング施策が功を奏した
指名検索の増加は、ユーザーが自社に対して高い関心を持っている証拠です。直接的なAI引用ではなくても、LLMOの間接的な成果として注目すべき指標といえるでしょう。
まとめ
本記事では、LLMOの概要やSEOとの違い、具体的な施策や効果検証の指標について詳しく解説しました。
今後、検索エンジンと生成AIが融合していく中で、LLMOは新しいSEOの一部として確実に広がっていく領域です。
時代の変化に柔軟に対応しながら、AI時代の情報発信に備えていきましょう。