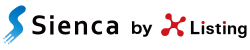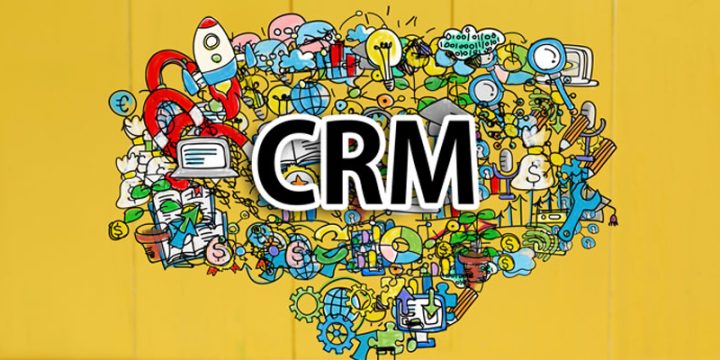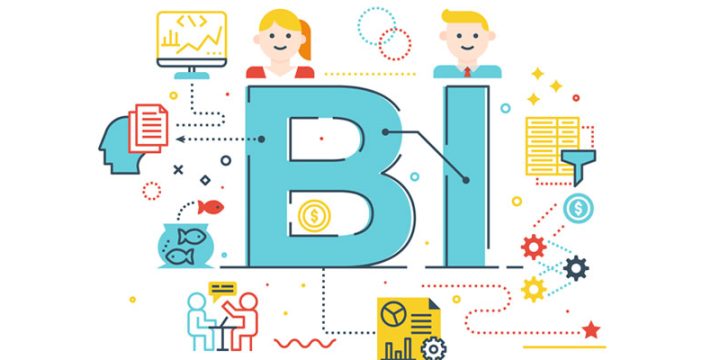データドリブンとは?重要性やメリット、具体的な方法をわかりやすく解説
データドリブンとは、感覚や経験ではなく、事実に基づいたデータをもとに意思決定や施策立案を行う考え方のこと。
近年は顧客行動の複雑化や分析技術の進化により、データドリブンを用いた分析・戦略立案手法はあらゆる業界で注目されています。
この記事では、データドリブンの意味や重要性、得られるメリット、実践のための4ステップ、活用できるツールまでをわかりやすく解説します。
マーケティング担当者や経営や企画の意思決定に関わる方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
データドリブンとは?
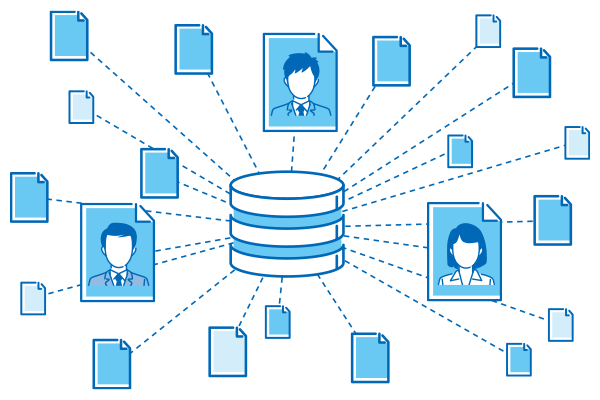
データドリブンとは、感覚や経験だけに頼らず、客観的なデータを基に意思決定や施策を行う考え方や手法のこと。わかりやすく言えば、「勘や思い込みで動くのではなく、数字や事実を根拠に動く」という姿勢です。
たとえば、これまでは「この広告は好評だったはず」という上層部の印象で継続していた施策も、クリック率やCVRといったデータを見れば効果の有無を客観的に判断できます。
データドリブンは単なる分析手法ではなく、意思決定の質と再現性を高めるための経営・マーケティングの土台といえます。
データドリブンが注目される理由
データドリブンは近年、多くの企業で取り入れられるようになっています。
その背景として挙げられる要因は、主に以下3つです。
- 顧客行動の複雑化
近年はSNSなどの複数の購買チャネルが普及し、顧客は多様な経路で情報収集・購買を行うようになっています。感覚頼りでは行動パターンを把握しきれないため、データによる裏付けが必要です。 - データ分析・活用技術の高度化
BIツールやAI分析など、以前は大企業しか使えなかった高度な技術が中小企業でも手軽に利用可能になりました。これにより、データドリブンのハードルが下がっています。 - 自社に合った戦略選択の重要性
競争が激しい市場では、他社の成功事例をそのまま真似しても成果が出にくくなっています。そのため、自社の顧客データを分析し、最適な戦略を選択する必要があります。
以上を踏まえると、競合他社や業界のスタンダードに遅れをとらないためには、今後はますますデータドリブンの重要性は増していくといえるでしょう。
データドリブンのメリット
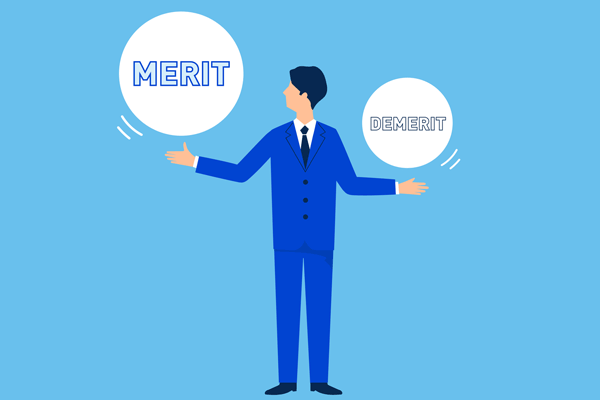
データドリブンを実践する主なメリットは、次の3つです。
- 再現性のある意思決定ができる
- 業務効率が上がる
- 顧客ごとに最適化されたマーケティングができる
ここからは、それぞれのメリットについて具体例を交えながら解説します。
再現性のある意思決定ができる
データドリブンの最大の利点は、再現性が高い意思決定が可能になることです。
感覚や経験則に基づく判断は、担当者のスキルや状況によって成果にばらつきが出やすい傾向があります。
一方、データを根拠とすれば、「どの施策がなぜ成果につながったのか」を明確に説明できるため、同じ施策で再び成果を出せる可能性が高まるでしょう。
たとえば、広告キャンペーンの成果をクリック率やコンバージョン率、顧客属性ごとに分析すれば、「どのチャネル・どのクリエイティブが効果的だったか」が数値でわかります。
その結果、次回以降のキャンペーンでも効果的なパターンを踏襲でき、安定的に成果を積み上げることが可能です。
業務効率が上がる
データドリブンを取り入れることで、無駄な業務や試行錯誤の時間を大幅に減らせるのも大きなメリットです。
担当者の経験に頼ったやり方では、効果検証や改善の方法が定まっておらず、成果につながるまで遠回りしてしまうことも少なくありません。
しかし、データを根拠にすれば、改善ポイントが明確になり、意思決定までのプロセスが短縮されます。
たとえば、広告運用で成果の低いキーワードや媒体がわかれば、配信を停止して効果の高い施策に予算を集中することが可能です。
顧客ごとに最適化されたマーケティングができる
データドリブンを実践すると、顧客一人ひとりの行動や嗜好に合わせたマーケティング施策が可能になるのもメリットの一つです。
たとえば、過去に高額商品を購入した顧客には上位モデルや関連商品の情報を、比較検討中の顧客には事例やレビューを重点的に配信する、といったアプローチをすることもできます。
これにより、顧客が求めているタイミングで最適な情報を届けられるため、コンバージョン率や顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
データドリブンを成功に導く4ステップ
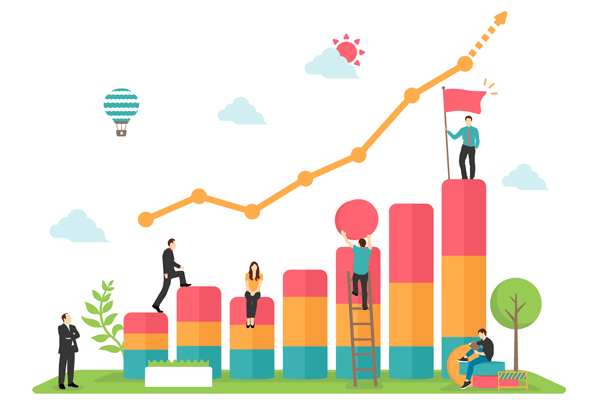
データドリブンを適切に行うには、「何となくデータを見る」だけでなく、データ収集から施策実行までのプロセスを一貫して設計することが大切です。
データドリブンの基本となる流れは以下のとおりです。
- データを収集する
- データを可視化する
- データを分析し、アクションプランを策定する
- アクションプランを実行する
ここからは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
データを収集する
データドリブンの出発点は、必要なデータを正確に集めることです。
集めるデータが不十分だと、その後の分析や施策も精度が落ちてしまいます。
MAツールやCRMなどから顧客データを集めるのはもちろん、マーケティング部門から過去の施策とその結果を収集するなど、必要なデータを漏れなく揃えましょう。
なお、データ収集の際は、施策の目的に沿ったデータだけを集めることが重要です。
むやみに項目を増やすと管理コストが上がり、必要な情報が埋もれてしまうので注意してください。
データを可視化する
次に、収集したデータを可視化するステップです。
グラフやチャート、ヒートマップ、ダッシュボードなどを用いて、誰が見てもデータから現状を把握できる形に整理しましょう。
このステップで重要なのは、目的に応じて指標や表示方法を絞り込むことです。関係のないデータまで盛り込みすぎると、分析の焦点がぼやけてしまいます。
なお、CDPやBIツール、Googleデータポータルなどを活用すれば、最新データを自動反映したダッシュボードを作成でき、リアルタイムで情報を可視化することが可能です。
データを分析し、アクションプランを策定する
次に、可視化されたデータをもとに、課題や改善の方向性を明確化するための分析を行います。
この段階では「何が起きているか」だけでなく、「なぜ起きているのか」という因果関係まで掘り下げることが重要です。
たとえば、広告のクリック率が高いのにコンバージョンが伸びない場合、ランディングページの内容やフォームの使い勝手に問題がある可能性があります。
こうした仮説をいくつも立て、必要なアクションプランを策定しましょう。
アクションプランを実行する
最後に、分析から導き出したアクションプランを実行しましょう。
実行の際は以下のポイントを意識してください。
- 期限と担当者を明確にする
- 成果指標(KPI)を設定する
- 進捗を定期的にモニタリングする
アクションプランは1回の実行で終わらせず、結果を再度データとして収集し、次の分析・改善サイクルに反映することが大切です。
PDCAサイクルを回し続けることで、施策の精度が徐々に高まり、安定的に成果を出せるようになります。
データドリブンを実践する際の注意点
データドリブンは成果を高める強力な手法ですが、実施するにあたっては以下のような注意点も存在します。
- データ活用に長けた人材が必要
データ収集や可視化はツールで自動化できますが、適切な指標を選び、分析結果から意味のある施策を導き出すには専門的な知識が欠かせません。 - 経営層・責任者層の理解が必要
データドリブンは、組織全体の方針や文化にも関わります。そのため、実践するには経営層が「感覚ではなくデータで判断する」という姿勢を示すことが不可欠です。
この2つを押さえたうえで、全社的にデータを軸とした意思決定の文化を定着させることが成功の鍵です。
データドリブンを支える7つのツール
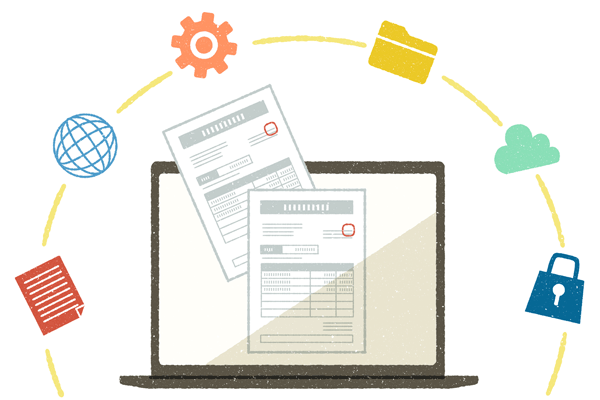
データドリブンを効果的に進めるには、データの収集・統合・分析・可視化をサポートするツールの活用が欠かせません。
ここでは、データドリブンに役立つ代表的な7つのツールとその役割をまとめて紹介します。
| ツール | 機能・できること |
|---|---|
| CDP | オンライン・オフラインの顧客データを一元管理することで、顧客理解を深められる。 |
| DMP | 広告配信やマーケティングに関する大量のデータを管理・分類できる。 |
| MAツール | 見込み顧客へのメール配信やスコアリングなど、マーケティング施策を自動化できる。 |
| SFA | 営業活動の進捗や案件を管理したり、営業プロセスを可視化したりできる。 |
| CRM | 顧客情報や履歴を管理し、長期的な関係構築やロイヤルティの向上を支援できる。 |
| BIツール | 膨大なデータを集計・分析・可視化し、経営や施策の意思決定を支援できる。 |
| Web解析ツール(GAなど) | サイト訪問者の行動データを取得・分析し、改善施策の立案に活用できる。 |
まとめ
データドリブンは、感覚や経験ではなく、事実に基づくデータを活用して意思決定や施策を行う考え方です。
顧客行動の複雑化や分析技術の進化により、現代のマーケティングや企業運営では欠かせない考え方となっています。
ただし、データドリブンを実践するには、データの管理や運用を適切に行わなければなりません。
そのため、社内にノウハウがない場合は、プロの支援を受けることも検討しましょう。
なお、当社ではCDPやBIツールなどを用いたデータドリブンなマーケティング活動の実現を支援しています。
データの管理・統合から実際の活用方法まで、一貫して支援させていただきますので、「データドリブンの考え方はわかったけど、どう取り組めばいいかわからない」という場合は、ぜひお気軽にご相談ください。