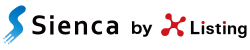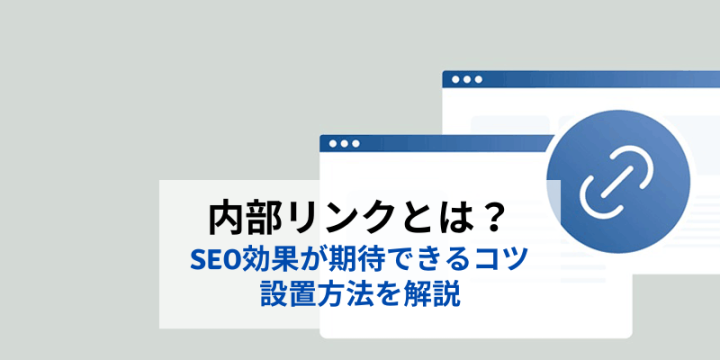AIO(AI Optimization)とは?SEOとの違いや具体的な対策ポイントを解説
「AIOって最近よく聞くけど、SEOとどう違うの?」
「自社サイトの流入が減ってきたけど、AI対応の対策が必要なのでは?」
生成AIの進化により、最近ではSEO(検索エンジン最適化)だけでなく、AIO(AI Optimization)という新しい概念が注目を集めています。
AIOとは、ChatGPTやGeminiなどのAIアシスタントに自社の正しい情報を理解・引用してもらうための最適化手法のこと。従来のSEO対策とは異なり、「AIがどう答えるか」に着目した新たな施策として注目を集めています。
この記事では、AIOの基本的な意味やSEOとの違い、AIO対策をすべき理由、そして今すぐ取り組める具体的な対策ポイントまで、わかりやすく解説します。
「AI時代に対応し、成果を出し続けるサイト運営をしたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
AIOとは?似た言葉との意味の違い
「AIO」と聞くと、ひとつの概念を指しているように思えますが、実は2つの異なる意味があります。
1つ目は「AIO=AI Optimization」です。これは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに対して、自社情報を正しく理解・引用してもらうための最適化施策を指します。
2つ目は「AIO=AI Overviews」です。こちらはGoogle検索に導入され始めているAIによる検索結果要約機能を指します。ユーザーに最初から簡易的な回答を提示することで、クリックなしで情報を得られる仕様になっています。
両者はどちらも「AIO」と呼ばれますが、意味は大きく異なるので注意しましょう。
なお、本記事では「AI Optimization」にフォーカスして詳しく解説していきます。

AIOとLLMO、GEOの違い
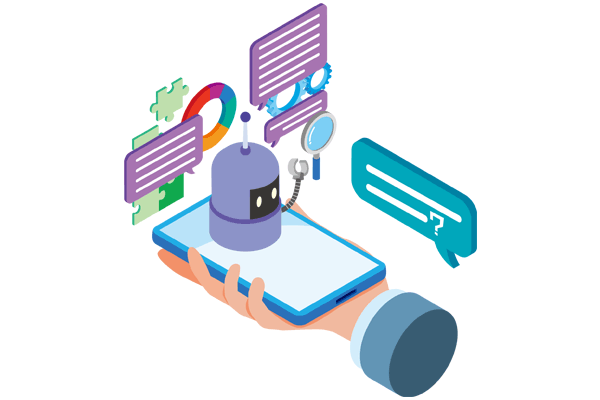
AIOと合わせて使われる用語として、LLMO(Large Language Model Optimization)やGEO(Generative Engine Optimization)といったものがあります。
これらは、いずれも生成AIの最適化施策ですが、最適化の対象や目的には違いがあります。
以下の表に、それぞれの特徴を整理しました。
| 用語 | 主な目的 | 対象 |
|---|---|---|
| GEO | 生成AIの回答に自社情報を表示させる | ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの検索AI |
| LLMO | LLMに正確な情報を学習・記憶させる | GPT-4やClaudeなどのLLMモデル本体 |
| AIO | 生成AIの回答に自社情報を表示させる | AI全般 |
ただし、AIに対する最適化施策はまだ新しい領域ということもあり「AIO=GEO=LLMO」として扱うケースも少なくありません。
それぞれの厳密な定義の違いについては、企業やメディアによっても解釈が異なるため、基本的には同じものと考えてよいでしょう。


AIO対策とSEO対策の違い
AIOとSEOは、どちらも「情報をユーザーに正しく届ける」ことを目的とした最適化手法ですが、対象となる媒体や評価軸、ゴールには明確な違いがあります。
以下の表で、両者の違いについて詳しく見ていきましょう。
| 項目 | AIO | SEO |
|---|---|---|
| 対象 | ChatGPTやGeminiなどの生成AI | GoogleやYahoo!などの検索エンジン |
| ゴール | AIによる回答文の中での引用や要約 | 検索結果の一覧ページ(SERPs)での上位獲得 |
| 評価軸 | サイト構造・文の明瞭さ・構造化データなど | キーワードの網羅性・コンテンツの質・被リンク・E-E-A-Tなど |
たとえば、SEOでは「検索結果の上位に表示されること」が重視されるのに対し、AIOでは「自社情報をどのようにしてAIに引用してもらうか」が鍵になります。
ただし、AIOとSEOでは共通している部分が多いのも事実です。
SEOで検索上位に表示されているページはAIにも参照されやすい傾向があるため「AIO=SEOの延長にある施策」ということを覚えておきましょう。
AIOが注目されている理由
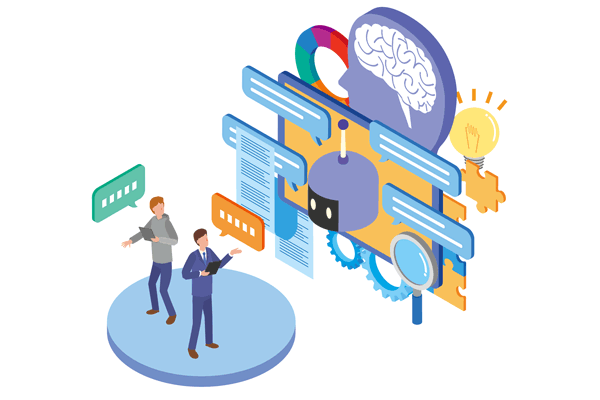
AIOが注目を集めている背景には、AI技術の進歩によるユーザー行動の変化があります。
特に近年は、「ゼロクリック検索」と呼ばれる現象が増加しています。
ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果に表示されたページをクリックせずに、GoogleのAI要約や生成AIの回答だけで満足してしまう検索行動のことです。
ゼロクリック検索自体は悪いことではありません。
しかし、Webサイト側からすると「せっかく検索上位に表示されても、ページを閲覧してもらえない…」という現象が起きています。実際、検索結果にAI要約が表示されるキーワードにおいて、CTRが通常の半分程度に低下したというデータもあるほどです。
そんな状況の中、AIの回答文の中に自社サイトのURLや自社名などを取り上げてもらい、ユーザーとの接点を持つ動きとしてAIO対策が注目を集めているのです。
AIOに取り組むメリット
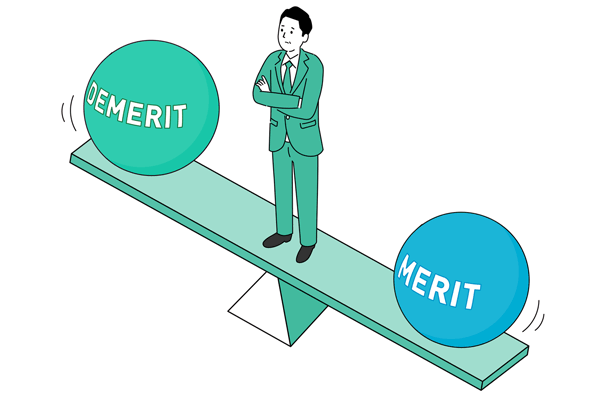
AIO対策には、単に「AI起点でユーザーと接点を持つ」という以外にもさまざまなメリットがあります。
具体的なメリットは、以下のとおりです。
- 生成AIでの情報露出が増える
ChatGPTやGeminiなどの回答に自社情報が含まれやすくなり、新たな流入経路が生まれます。 - ゼロクリック時代でも認知を獲得できる
検索をしてもクリックされない時代においても、AIによる回答内で言及されることでユーザーの記憶に残る可能性が高まります。 - AI時代に適したコンテンツ設計が進む
論理構造やE-E-A-Tの強化などを意識した結果、コンテンツ全体の質が向上し、SEOにも良い影響を与えることがあります。 - 今後のAI検索・自動要約機能への布石になる
AI Overviewsなどの新機能が広がる中で、早期にAIOを実践しておくことで先行優位を築きやすくなります。
AIOは「次世代の情報発信戦略」として捉えられがちですが、今後AIの普及がさらに進むことによって、重要性が増していくことが予想されます。
そのため、ライバルが少ない段階から取り組むことに大きな意味があるでしょう。
AIOに取り組むデメリット
AIOは注目度の高い施策ではありますが、取り組みにあたってはいくつかの注意点やデメリットも存在します。
導入を検討する際には、以下のような点を踏まえておくとよいでしょう。
- 効果の可視化が難しい
AIOの効果検証指標として、実際の引用・参照数などがありますが、現状効果測定ツールなどが少なく、自力での検証が難しいケースがほとんどです。 - 継続的な試行錯誤が必要
AIの進化は早く、どのような情報が引用されるかも日々変化しています。そのため、定期的な更新と改善を続ける必要があります。 - SEOと比べてまだノウハウが少ない
AIOは比較的新しい概念のため、成功事例や明確なノウハウが少なく、自社で試行錯誤しながら取り組む必要があります。
このように、AIOには将来的な効果が期待できる一方で、短期的な成果が見えにくい点や、体制・知見の不足が障壁になる可能性もあるのです。
今からできるAIO対策5選
「AIOの重要性はわかったけれど、具体的に何をすればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
AIOは特別なツールや高度なAI知識がなくても、今あるコンテンツやWebサイトの見直しから着手できます。
ここでは、SEO担当者やWeb運用者がすぐに実践できるAIO対策として、以下5つを紹介します。
- AIが引用しやすいコンテンツの作成
- E-E-A-Tの向上
- サイテーション、被リンクの獲得
- ブランディング・PRによるエンティティ強化
- 構造化データマークアップ
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
AIが引用しやすいコンテンツの作成
AIOにおいて最も基本となるのが、生成AIがそのまま引用しやすい構造の文章・コンテンツを作ることです。
ChatGPTやGeminiなどのAIは、人間のように自由に文脈を解釈しているわけではなく、明快な構造や明示的な記述を重視して情報を抽出しています。
具体的に、AIに引用されやすくするためには以下のような工夫が効果的です。
- 結論ファーストで要点を明確に書く
- FAQやQ&A形式の見出しを活用する
- 1段落1テーマで、簡潔な文を心がける
- 表や箇条書きで情報を整理する
たとえば、「AIOとは?」という見出しの直後に「AIOとは、生成AIに自社情報を正しく伝えるための最適化手法です。」という一文があれば、そのままAIが回答文に引用しやすくなります。
また、FAQページや「~とは?」などの定義型コンテンツはAIが構造を把握しやすいため、積極的に取り入れるとよいでしょう。
E-E-A-Tの向上
生成AIに自社情報を信頼してもらうためには、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の向上も欠かせません。
E-E-A-Tは、SEOでも重要視される評価基準ですが、AIOにおいてもAIが「誰の情報か」「どれだけ信頼できるか」を判断する根拠になります。
E-E-A-Tを高めるための具体的なポイントは以下のとおりです。
- 著者や監修者のプロフィールを明示する
専門的な立場や実績がある人物による発信であることを明記する。 - 一次情報や経験に基づいた内容を盛り込む
実体験や実績データを含める。 - 外部ソースや権威あるデータを引用する
公的機関や業界団体など、信頼できる情報源へのリンクを設ける。 - 古い情報を定期的に更新する
情報の鮮度もAIが評価する要素の一つです。
AIは、表面的な情報量よりも「誰が、なぜその情報を発信しているのか」に注目しています。
そのため、E-E-A-Tを意識したコンテンツを作成することで、回答文で引用・参照してもらえる機会を増やすことにつながるでしょう。
サイテーション、被リンクの獲得
AIOにおいて重要なのは、自社サイトの内容そのものだけでなく、外部のサイトでどれだけ言及(サイテーション)されているかという点です。
生成AIは、Web上で繰り返し言及されている情報を「信頼性の高い情報」と判断しやすく、回答文への引用対象として優先しやすくなります。
また、被リンクも従来のSEOにとどまらず、AIが情報源を判断するうえでの有力なシグナルになります。
そのため、以下のような施策によってサイテーションや被リンクの獲得を目指すことが大切です。
- 業界メディアやポータルサイトでの紹介記事掲載
- プレスリリースの継続的な発信
- 他社ブログや比較サイトでの言及・レビュー獲得
- SNSや口コミサイトでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)の拡散
なお、言及先で自社サイトに向けたリンクが貼られていなくても、社名・サービス名などが信頼性の高いサイトで繰り返し登場していれば、AIに学習・引用される確率は高まります。
AIO対策では、「自社サイト内の最適化」に加えて、「外部サイトからどのように語られているか」を意識した取り組みも不可欠だということを覚えておきましょう。
ブランディング・PRによるエンティティ強化
生成AIが情報を引用・認識する際に重要視するのが「エンティティ(固有名詞)としての明確な存在感」です。
たとえば、ネット上で「コンビニといえば、セブンイレブン」のように「特定のサービス=自社」というような存在感を生み出すことができれば、自然とAIによって引用・紹介される機会も増えていきます。
そのため、AIO対策では自社名やブランド名が「何者か」をWeb上で定義するための取り組みを行うことが大切なのです。
具体的には、以下のようなブランディングやPRなどの継続的な活動が有効です。
- 社名・ブランド名・サービス名を統一して使用する
- 公式情報(会社概要・SNSアカウント・著者情報など)を明確に整備する
- メディア掲載やインタビュー記事などで“第三者視点”から語られる機会を増やす
- GoogleビジネスプロフィールやWikipediaなどへの掲載も検討する
- テレビやYouTubeなどでCMを配信する
SEO的な視点だけでなく、ブランドがWeb上で“定義されているか”という視点を持つことで、AIOの効果を高めやすくなります。
構造化データマークアップ
構造化データとは、Webページ内の情報を検索エンジンやAIが「機械的に理解しやすい形式」に変換するための記述方式です。
適切な構造化データで記述することで、生成AIに対しても「このページは誰が、何について書いたものか」を明確に伝えることができます。
AIO対策として効果的な構造化データの例は、以下のとおりです。
| 構造化データの種類 | 用途・効果 |
|---|---|
| Organization | 会社名・ロゴ・住所・SNSリンクの明示 |
| Article | 著者・投稿日・ジャンルなどの記事情報の整理 |
| FAQPage | 質問と回答のセットをAIに正確に伝える |
| Product | 商品名・価格・レビュー・在庫情報の表示 |
| Person | 執筆者や監修者の肩書やプロフィールの明記 |
なお、構造化データはSEO対策とAIO対策の両方に貢献する施策です。
Googleが提供する構造化データテストツールや、Schema.orgを活用して、AIが正確に情報を読み取れる状態を整えておきましょう。
AIOに取り組む際の注意点
AIOは今後ますます重要になる施策ですが、注意点として「すべてのキーワードやページに対して必ずしも必要というわけではない」ということを覚えておきましょう。
なぜなら、ニッチなキーワードや競合が少ない領域では、従来のSEOだけでも十分に成果が得られるケースがあるからです。
AIO対策が必要かどうかで悩んだときは、実際にGoogleで検索してAI Overviewsが表示されるかどうかや、ChatGPTなどにキーワードで質問してみて、その回答を確認してみましょう。
AI Overviewsが表示されていなかったり、AIからの回答が明確でなかったりする場合は、まだAIO対策をするには早いかもしれません。
もちろん、「他社に対策される前に自社で対策しておきたい」という考え方もできますが、成果を第一に考えるなら、必要なキーワードでだけAIO対策を行い、それ以外はこれまで通りSEOにリソースを投下するなど、適切な運用が大切です。
AIOの今後の展望
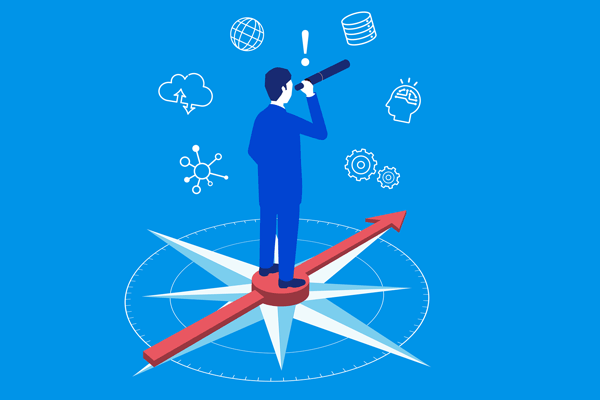
今後、AIOはSEOと並ぶ、あるいはそれ以上に重要な情報最適化の手法として広がっていく可能性があります。
すでにGoogleは「AI Overviews」の本格導入を進めており、検索体験そのものが「リンクを探す」から「答えを得る」ものへと大きく変わりつつあります。
それに伴い、企業やメディアの情報が生成AIによる要約・引用を通じてユーザーに届く時代が本格的に到来しています。
また、AIO・GEO・LLMOといった分野に特化したコンサルティングや支援サービスを提供する企業も増加中です。
ツールやナレッジの整備も進み、今後は中小企業でもより手軽にAIOに取り組める環境が整っていくでしょう。
検索行動がAI中心にシフトしていく中で、AIOは「AI時代における新たな情報露出戦略」として、今後さらに注目を集めるはずです。
まとめ
本記事では、AIO対策について類義語の違いやメリット・デメリット、具体的な施策までわかりやすく解説しました。
AIOは、生成AI時代において自社情報を正確に届けるための新たな最適化手法です。
SEOが検索エンジン向けの対策であるのに対し、AIOはChatGPTやGeminiといったAIに“どう理解され、どう引用されるか”を意識した施策といえます。
AI検索や要約機能の普及により、従来の検索上位だけではユーザーと接点を持ちにくくなっている今、AIOへの取り組みはますます重要になっています。
これからAIOに取り組む方は、まずはAIにとって“読みやすく・引用しやすい”コンテンツ作りから始めてみてはいかがでしょうか。
AI時代に取り残されないためにも、今のうちからAIOを意識したコンテンツ設計を進めていきましょう。